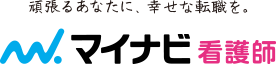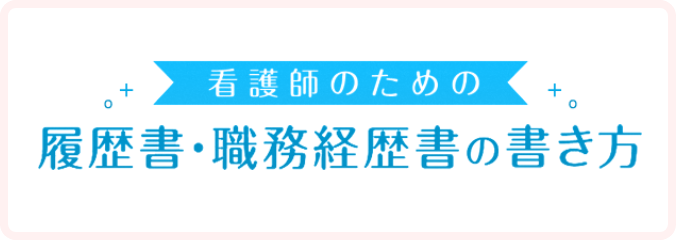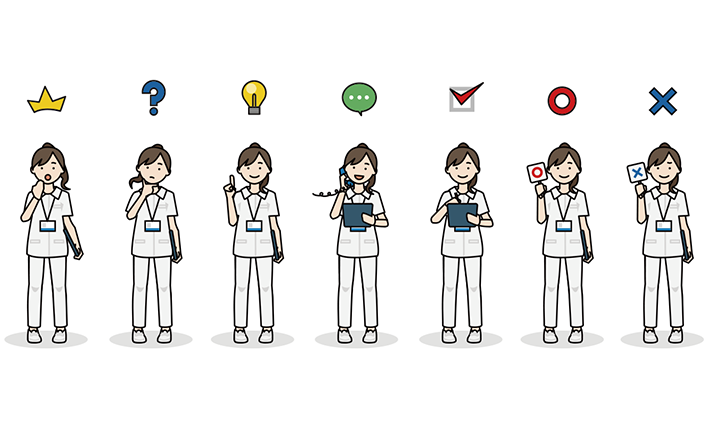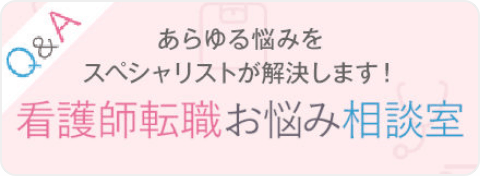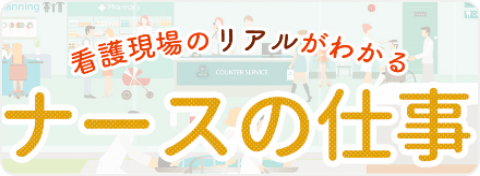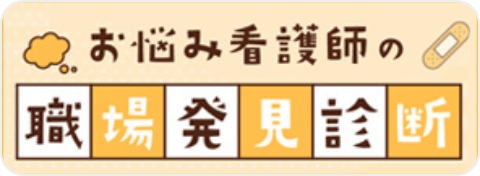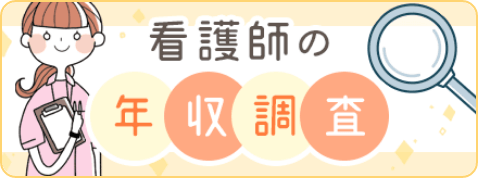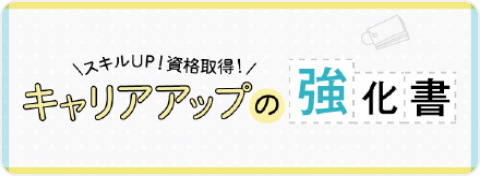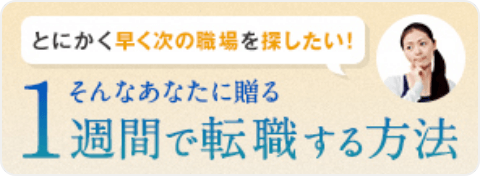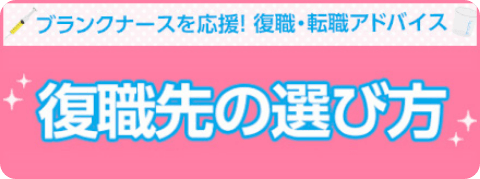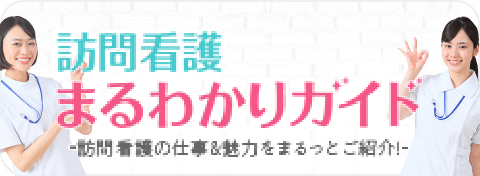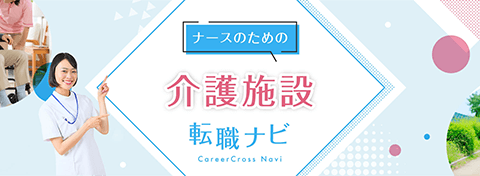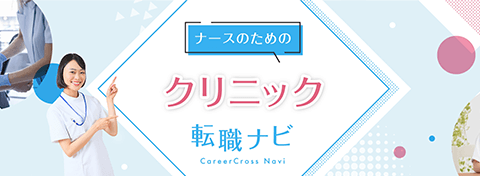看護師が地域医療に関わるには? 地域での活躍や訪問看護について解説
近年、高齢化社会が進む日本では地域医療が重要視されています。地域と医療・介護との連携が必要な地域医療では、看護師もさまざまな現場で活躍ができます。「地域看護学」という学問も存在し、地域の人々の健康面のサポートをどのように行うか考えていくことが大切です。
当記事では、地域医療と看護師の関わり方について詳しく解説します。地域に密着し、患者さん一人ひとりと深くかかわる看護をしていきたい方はぜひご覧ください。
1.看護師がかかわる地域医療

地域医療とは、保健・医療・福祉が連携しながら医療を行っていくことを意味します。地域医療は、高齢化社会においてますます重要性が高まっています。特に高齢者が多い地域では、認知症や寝たきりなど介護が必要な状態になることが多く、医療と地域自治体との密な連携が必要です。
少子高齢化の加速スピードが早くなる未来を見据え、クオリティの高い医療を効率よく提供できる体制の構築を目指して、日本では地域医療が推進されています。地域医療を実現させるために、地域医療構想や地域包括ケアシステムが構築されています。
1‐1.地域医療構想とは
少子高齢化の加速に伴い必要となる医療サービスの変化や、医療従事者数の減少が見込まれるので、地域医療構想が厚生労働省により制度化されました。質の高い医療サービスを効率よく提供するには、医療機関を機能ごとに分け、地域との連携を進める必要があります。
団塊世代が75歳を迎え、医療と介護の需要が最大に達すると推測される2025年の医療体制を考慮し設計されている制度です。地域医療構想は、全日本病院協会により以下のように定義されています。
地域医療構想は、将来人口推計をもとに2025年に必要となる病床数(病床の必要量)を4つの医療機能ごとに推計した上で、地域の医療関係者の協議を通じて病床の機能分化と連携を進め、効率的な医療提供体制を実現する取組みです。
地域医療構想が必要な理由として、以下のような点が挙げられます。
- 病院を退院した患者さんが地域で安心して療養生活を送れるようにするため
- 住み慣れた地域での在宅療養を安心・安全に継続するため
- 症状や状態に合った質の高い医療サービスを全国とこでも同じように受けられる体制を整えるため
地域医療構想は、地域全体で住民の健康づくりをサポートする医療体制であることから、従来の医療とは異なり、地域との密な連携が必須です。また、特定の病院や医師以外にも、さまざまな医療機関や福祉などの多職種が協働して取り組むことが求められます。
(出典:厚生労働省「地域医療構想策定ガイドラインについて」)
1‐2.地域包括ケアシステムとは
地域包括ケアシステムとは、重度な介護が必要になったとしても住み慣れた地域で暮らせるように支援するためのシステムです。医療や介護、福祉、住宅、行政など、さまざまな分野の専門家や団体が連携し、地域全体で支援体制を構築します。つまり、介護保険制度と医療保険制度の両分野を利用し地域全体で高齢者を支えるシステムであるといえます。
地域包括支援センターとは、高齢者が受ける保健医療水準の向上や、福祉の増進を総合的に支援することを目的とした施設です。地域包括ケアシステムの実現に向けた中核的な機関として、市町村が主体で運営しており、地域包括ケアシステムの一翼を担っています。
施設で実施される主な内容は、地域に住む高齢者の普段の生活なども含めた総合的な相談の受付や、介護予防に必要な支援などです。また、利用者さんのケアプラン作成や介護サービスの利用方法のアドバイス、介護保険制度に関する説明なども行っています。
(出典:公益社団法人 全日本病院協会「地域包括ケアシステム」)
1‐3.地域看護とは
地域看護の目的は、地域で暮らす人々の健康と安全を支援し、これまでの生活を変えない暮らしを保証しながら、生活の質を向上させることです。地域看護学は、人々の生活の質向上と、健康で安全な地域社会の形成に効果的な看護を探求する学問です。保健師、助産師、看護師の看護職に同じように求められる知識や能力を養うのに必要な基本となる学問として位置づけられています。
地域看護では生活者のいるすべての場所が活動範囲となり、さまざまな健康レベルの方を対象とするため、対象となる集団や場所の特徴により看護の展開方法は異なります。高齢化や少子高齢化、地方の医療格差など、さまざまな社会的課題に直面する現代社会においてとても重要です。
実際には、医療機関や診療所などの施設から離れた地域で暮らす人に対し、病気の予防や健康管理、リハビリテーションなどを行います。また、その地域独特のニーズや特性を理解し、地域住民との信頼関係を構築しながら健康相談や健康教育、予防接種などを実施します。治療やリハビリテーション、訪問看護や在宅ケアなど多様なニーズに応えることが求められるので、地域の医療機関や介護施設、地域包括支援センターなどとの連携も重要です。
(出典:一般社団法人 日本地域看護学会「地域看護学の再定義」)
転職・復職に悩んだら、まずはマイナビ看護師にご相談ください。
業界を熟知したキャリアアドバイザーと一緒に、
理想の転職を叶えましょう!
転職・復職に悩んだら、
まずはマイナビ看護師にご相談ください。
業界を熟知したキャリアアドバイザーと一緒に、理想の転職を叶えましょう!
2.看護師が行う訪問看護とは

訪問看護とは、看護師が患者さんの自宅などを訪問し、医師から指示された医療行為や、日常生活におけるサポートを提供する看護の一種です。病気や障がい、慢性的な疾患を抱えるために外出が困難な患者さんに対し、必要な看護を提供して自宅での生活を支援します。また、患者さんの家族とも信頼関係を構築しながら、自宅で最後まで暮らせるよう療養生活を手助けすることも重要な業務です。
具体的には、薬の管理や緊急時の対応、傷の処置や点滴、バイタルチェックや各種検査などの医療的ケアだけでなく、排せつや食事、入浴などの生活援助を行います。また、患者さんや家族に対し、看護師の視点から健康管理に関するアドバイスを行うこともあります。
訪問看護は、高齢化社会においてますます需要が高まっており、地域包括ケアシステムにおいて欠かせないサービスの1つです。
(出典:公益財団法人 日本訪問看護財団「訪問看護とは(医療・福祉関係者向け)」)
2‐1.在宅看護との違い
在宅看護とは、自宅での療養が可能な場合に、病院ではなく自宅で家族が看護することを指します。近年、QOL向上や患者さんの意志を尊重するため、病院での療養から在宅療養へと療養環境の移行を推奨する動きが高まっています。
訪問看護とは違い、家族が主体となり看護を行うので、医療行為はできません。また、在宅看護の場合は緊急時に備え、24時間受け入れできる医療機関を見つけておく必要性があります。
家族はかかりつけ医と相談しながら看護を行いますが、患者さんの状況に応じてデイケアサービスや訪問介護支援を受けることも可能です。在宅看護の具体的なサービス内容としては、療養環境へのアドバイスや、状態観察、療養上の悩み相談などの家族への支援が挙げられます。
2‐2.訪問介護との違い
訪問介護とは、訪問介護員が利用者さんの自宅を訪問し、入浴や排せつ、生活サポートを行うことを指します。サポートの主な内容は、「身体介護」と「生活援助」の2つです。
身体介護は、利用者さんの身体に直接接触して行われるサービスで、日常動作や意欲向上を目的にした自立支援のためのサービスです。生活援助は、掃除や洗濯、買い物や調理など、日常生活の中の支援内容を指し、本人もしくは家族が家事を行うことが難しい場合に行われます。
訪問介護の対象となるのは、要介護1以上の認定を受けた方です。訪問看護と違い、訪問介護は医療ケアではなく日常の生活支援が主なサービスの内容です。
(出典:厚生労働省「どんなサービスがあるの?-訪問介護(ホームヘルプ)」)
転職・復職に悩んだら、まずはマイナビ看護師にご相談ください。
業界を熟知したキャリアアドバイザーと一緒に、
理想の転職を叶えましょう!
転職・復職に悩んだら、
まずはマイナビ看護師にご相談ください。
業界を熟知したキャリアアドバイザーと一緒に、理想の転職を叶えましょう!
3.地域医療にかかわる看護師の活躍場所
看護師さんにとって、地域医療にはさまざまなかかわり方があり、活躍の場も多くあります。ここでは、各地域医療の現場で看護師の皆さんがどのような場所で働いているのかを紹介します。
ほかの方の働き方を参考に、ご自身の理想とする働き方ができるかをぜひ確かめてください。
3‐1.急性期病院
急性期病院とは、救急隊によって搬送される患者さんの担当する病院で、急性疾患または重症の場合の治療を24時間体制で行う病院を指します。
急性期病院で働く魅力として、医師や連携先の医療機関、介護施設の職員などと協議会を行い、患者さんや家族が安心して暮らせるよう地域連携を図れる点が挙げられます。特に、搬送後の在宅復帰には看護師の皆さんのサポートが必要不可欠なため、やりがいにもつながるでしょう。急性期病院では、認定看護師が患者さんの退院支援や社会復帰に向けた看護指導を行うケースも多くあります。
認定看護師とは、特定の看護分野において深い知識と熟練した看護技術を持つ看護師を指します。認定看護師になるには、看護師として5年以上の実務経験が必要です。その後日本看護協会が定める認定看護師教育を修め、認定看護師認定審査に合格すると取得できます。
認定看護師制度は、高水準の看護を実践できる認定看護師を社会に送り出して看護ケアの拡充と質の向上を図ることが主な目的です。認定看護師は病院のほかに、訪問看護ステーションやクリニック、診療所や介護保険施設などにも活躍の場があります。
(出典:公益社団法人 日本看護協会「専門看護師・認定看護師・認定看護管理者」)
3‐2.地域の医療機関
地域の医療機関には、地域連携室が設置されているケースがあります。地域連携室とは、大きな病院と地域医療との連携に必要な業務を行う部署を指します。大きな病院に軽症の患者さんも集中した結果、待ち時間が長くなることや重症の患者さんに十分な時間を当てられなくなることを防ぐために作られました。
地域連携室では、患者さんが地域の医療機関や施設へスムーズに移れるよう、医療機関だけでなく介護施設や行政、福祉などさまざまな機関と連携し業務を行います。患者さんが退院する際には、退院後の生活について相談を受け、福祉施設などと連携し在宅療養や施設入所のサポートを行うことが仕事です。
地域連携室で働くと、地域住民の健康に関する問題を把握でき、健康増進支援を直接的に提供できます。また、患者さんの退院後の生活を支えるために必要な情報共有やコミュニケーションが必要であり、地域の課題やニーズを把握することも可能です。
地域連携室の仕事内容は比較的新しく、近年注目されている分野でもあり重要な役割を担っているため、働く中で大きなやりがいを感じられるでしょう。
3‐3.デイサービスセンター
デイサービスセンターとは、介護保険において要介護1〜5の認定を受けている高齢者が日帰りで通う介護施設を指し、正式には「通所介護」といいます。デイサービスでは、要介護状態になった方の生活の質を向上させ、自立した生活を送るための支援を目的としています。介護サービスや機能訓練の実施により、利用者さんの心身機能の維持と尊厳回復を図るだけでなく、家族の介護負担を減少させることが主な役割です。
(出典:厚生労働省「どんなサービスがあるの? – 通所介護(デイサービス)」)
多くのデイサービスセンターでは専用車による送迎を行っており、自分で施設に通えない方でも利用できます。単独での外出が難しくなると自宅にこもりやすくなりますが、デイサービスセンターに通うことでほかの方との交流やリハビリを受けられます。
デイサービスセンターには医師の配置が義務付けられておらず、看護師さんはデイサービスの利用者さんの医療サポートにおいて大きな役割を担います。主な業務内容としては、利用者さんの健康管理で、具体的にはバイタルチェックや服薬管理、口腔ケアや応急対応などが挙げられます。介護に関心のある看護師さんに向いている職場といえるでしょう。
3‐4.訪問看護センター
訪問看護とは、自宅療養する患者さんの自宅へ看護師さんが訪問し、ケアをするサービスです。訪問看護師さんは、患者さんやご家族の「自宅で過ごしたい」という意志を尊重し、自宅での暮らしの実現に向け、専門性を活かし予防から看取りまでを支えます。
実際の業務では、主治医が作成する訪問看護指示書に基づいて、健康観察や医療ケア、緩和ケアやリハビリなどを行います。ほかにも、患者さんやそのご家族の不安や相談を聞き、アドバイスすることも重要な業務です。乳幼児から高齢者までと対象は広く、診療科も内科だけでなく脳神経科やリハビリに特化したケア、ターミナルケアなど広範囲に渡ります。
近年、在宅医療を利用する方が増えており、訪問看護センターで働く看護師さんのニーズが高まっています。患者さんと直接関わり、一人ひとりに必要なケアを行えるため、患者さんの状態や生活環境を把握し、個別の対応が可能です。患者さんのニーズに合わせた看護を提供すると、患者さんからの信頼や感謝の言葉を得られることもあるでしょう。
転職・復職に悩んだら、まずはマイナビ看護師にご相談ください。
業界を熟知したキャリアアドバイザーと一緒に、
理想の転職を叶えましょう!
転職・復職に悩んだら、
まずはマイナビ看護師にご相談ください。
業界を熟知したキャリアアドバイザーと一緒に、理想の転職を叶えましょう!
4.地域医療の課題

今後少子高齢化が進む中で、医療機関と地域が密に連携し症状や状態に合った適切なサービスが受けられる状態を構築するためにも、地域医療は重要です。しかし、地域医療にはいくつかの問題点や課題があります。
ここでは、地域医療の課題について詳しく解説します。
4‐1.人材不足
高齢化社会に伴い地域医療の重要性が高まっている中で、訪問看護師さんの人手不足が深刻な課題です。看護師として働いている方の中で、訪問看護職員として働いている方は約2%にとどまっています。
(出典:公益社団法人 日本看護協会「地域における訪問看護人材の確保・育成・活用策に関する調査研究事業報告書」)
人手不足の理由として、訪問看護では患者さんの自宅を訪問し看護を行うため、訪問先で求められるケアの多様性や移動の問題など、看護師さんの負担が大きい点が挙げられます。そのため多くの看護師さんが長時間労働や過重労働に陥りやすい状況であることが問題となっています。
また、訪問看護の業務は高度な専門性を必要としており、豊富な経験やスキルを積んだ看護師さんの確保が必要です。しかし、訪問看護の業務に対応できるだけのスキルや専門性を持つ看護師さんの数は限られている点も、人手不足に陥りやすい原因の1つです。
訪問看護師の業務負担の軽減や、訪問看護師の育成、採用の促進など、積極的な対策を行う必要があります。また、地域医療の充実に向けて、訪問看護師の役割や貢献度の高さを広く認知することも、訪問看護師の人手不足解消に向けた取り組みとして重要です。
4‐2.スキル不足
訪問看護は訪問先で医療的なケアを行う必要があり、看護師としての高いスキルや知識が求められます。しかし、訪問看護師のスキル不足が、地域医療における課題となっています。
まず、訪問看護師は患者さんの自宅で看護を行うため、自己判断力や判断基準を持っていることが重要です。しかし、現状の訪問看護師のなかには、判断力や判断基準が不十分な場合があり、患者さんの状態を適切に把握できず、適切な医療処置を行えない場合もあります。
また、訪問看護では患者さんとの密なコミュニケーションが重要です。しかし、患者さんとのコミュニケーションに慣れていない場合、患者さんと信頼関係を築けず、適切な医療処置が難しくなる場合もあります。
訪問看護師として働くうえで、スキルや知識は非常に重要ですが、特定の分野の知識を身に着けることも有効です。特に、認定看護師や専門看護師、ケアマネジャーの資格などを取得しておけば、知識を深められ、より活躍の幅を広げられるでしょう。
転職・復職に悩んだら、まずはマイナビ看護師にご相談ください。
業界を熟知したキャリアアドバイザーと一緒に、
理想の転職を叶えましょう!
転職・復職に悩んだら、
まずはマイナビ看護師にご相談ください。
業界を熟知したキャリアアドバイザーと一緒に、理想の転職を叶えましょう!
まとめ
地域医療とは、地域にある医療機関の役割分担を行い、保健・医療・福祉が連携しあって医療体制を整えていくことを指します。看護師も急性期病院での看護指導や、訪問看護の現場で地域医療と関わっていく必要があります。特に訪問看護の現場は人手不足が叫ばれており、看護師のニーズが高まっています。
マイナビ看護師では、訪問看護をはじめとして、さまざまな地域での求人を掲載しています。看護職専門のキャリアアドバイザーによるサポートも受けられるので、転職を検討している看護師さんはぜひマイナビ看護師をご利用ください。
※当記事は2023年3月時点の情報をもとに作成しています
転職・復職に悩んだら、まずはマイナビ看護師にご相談ください。
業界を熟知したキャリアアドバイザーと一緒に、
理想の転職を叶えましょう!
転職・復職に悩んだら、
まずはマイナビ看護師にご相談ください。
業界を熟知したキャリアアドバイザーと一緒に、理想の転職を叶えましょう!
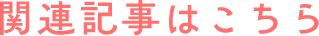 関連記事はこちら
関連記事はこちら
Related article
-

2018年度 診療報酬・介護報酬ダブル改定の要点 <各論4:在宅医療・訪問看護の質量両面での拡充が急務>
ヘッドラインニュース2022.09.29
-

チーム医療のあり方が変化!看護師の働き方は変わった? 第6回
ヘッドラインニュース2022.09.29
-

看護師の働き方|勤務先ごとの特徴と働き方に関するよくある悩み
キャリアアップの強化書2022.09.29
-

訪問看護での働き方
復職先の選び方2021.01.15
-

訪問看護師とは? 仕事内容やメリット・デメリットを詳しく解説
キャリアアップの強化書2023.12.27
-

チーム医療で看護師が果たす役割|チーム医療の概要から必要性まで
キャリアアップの強化書2023.12.28
 人気記事ランキング
人気記事ランキング
Ranking
 新着・注目のコンテンツ
新着・注目のコンテンツ
New arrival・Featured
転職・復職に悩んだら、
まずはマイナビ看護師にご相談ください。
業界を熟知したキャリアアドバイザーと
一緒に、
理想の転職を叶えましょう!
ニュース・コラム
診断ツール
転職・キャリアアップ
業界研究
看護師の求人を資格から探す
看護師の求人を勤務形態で探す
看護師の求人を雇用形態で探す
看護師の求人を施設形態で探す
看護師の求人を担当業務で探す
看護師の求人を診療科目で探す
看護師の求人をこだわりで探す
看護師の求人を勤務地で探す
看護師の求人を資格から探す
- 看護師の求人 |
- 准看護師の求人 |
- 助産師の求人 |
- 保健師の求人 |
- ケアマネージャーの求人
看護師の求人を勤務形態で探す
看護師の求人を雇用形態で探す
看護師の求人を施設形態で探す
- 病院 |
- 急性期病院 |
- ケアミックス型病院 |
- 療養型病院 |
- 精神科病院 |
- 精神科クリニック |
- 精神科訪問看護 |
- 検診センター |
- クリニック・診療所 |
- 美容クリニック |
- 老人ホーム・特養・老健などの施設 |
- 訪問看護ステーション |
- 看護師資格・経験を活かせる一般企業 |
- 治験関連企業(CRA、CRCなど) |
- 保育施設(保育園) |
- リハビリテーション病院
看護師の求人を担当業務で探す
看護師の求人を診療科目で探す
看護師の求人をこだわりで探す
- 未経験歓迎 |
- 復職・ブランク可 |
- 寮・借り上げ社宅あり |
- 住宅補助・手当あり |
- 託児所・保育支援あり |
- 産休・育休実績あり |
- 資格取得支援あり |
- 電子カルテあり |
- 副業OK |
- 土日・祝日休み |
- 4週8休以上(または週休2日以上) |
- 駅チカ(徒歩10分以内) |
- マイカー通勤可・相談可 |
- 残業10h以下(ほぼなし) |
- 年収500万円以上可 |
- 年間休日多め |
- 1月入職可能 |
- 4月入職可能 |
- 夏~秋入職可 |
- オンコールなし |
- 他業種・他職種への転職 |
- 積極採用中 |
- WEB面接OK |
- 管理職 |
- トラベルナース