
在職中は年金保険料、健康保険料、雇用保険料、税金などが給与から自動的に天引きされていましたが、退職すると厚生年金や健康保険の被保険者資格を喪失することになり、いくつかの手続きを退職者自身で行う必要が出てきます。この手続きを怠ると、医療費が全額負担になったり、受給できるはずの失業手当(雇用保険の基本手当)が受け取れなかったりして、大きな損失を被るおそれがあります。ついつい後回しになりがちですが、重要な手続きですから早めに済ませておきましょう。
転職時の手続き|お役立ちガイド | 【マイナビ看護師】≪公式≫看護師の求人・転職・募集

在職中は年金保険料、健康保険料、雇用保険料、税金などが給与から自動的に天引きされていましたが、退職すると厚生年金や健康保険の被保険者資格を喪失することになり、いくつかの手続きを退職者自身で行う必要が出てきます。この手続きを怠ると、医療費が全額負担になったり、受給できるはずの失業手当(雇用保険の基本手当)が受け取れなかったりして、大きな損失を被るおそれがあります。ついつい後回しになりがちですが、重要な手続きですから早めに済ませておきましょう。
自分に必要な手続き(年金、健康保険、失業手当)を知ろう
失業期間の有無や、雇用保険の加入期間によって必要な手続きが異なります。自分がA~Cのどのパターンに該当するかに応じて、必要な手続きをチェックしましょう。
転職先の職場が代行してくれるため、自分で手続きする必要はありません。転職後に、雇用保険被保険者証、年金手帳、源泉徴収票などを職場に提出しましょう。失業期間が存在しないため、失業手当は給付対象外です。
「年金」と「健康保険」の切り替え手続きが必要です。雇用保険の加入期間が短いため、失業手当を受給することはできません。
「年金」と「健康保険」の切り替え手続きが必要です。過去2年間で通算12カ月以上雇用保険に加入していた場合は、失業手当を受給できる可能性があるので手続きを進めましょう。
切り替えは二者択一!「年金」の手続き方法
公的年金の被保険者には、次の3つの種類があります。
国民皆保険の原則に基づき、20歳から60歳までの国民は失業期間中も国民年金に加入し、被保険者となる必要があります。在職中に厚生年金に加入していた第2号被保険者が退職した場合に行うのは、第1号被保険者または第3号被保険者への切り替え手続きです。通常は第1号被保険者となりますが、条件を満たす場合には国民年金保険料が不要の第3号被保険者になることもできます。
・手続きの期間:退職後14日以内 ・手続きの場所:市区町村役所・役場の国民年金窓口 ・必要なもの:年金手帳、印鑑、離職票や退職証明書など退職日が確認できる書類
退職日が月末でない場合は、残日数が少なくても退職した月の分から保険料を納付する必要があります。当年度の所得が少なくて保険料の納付が難しい場合などには、退職(失業)による国民年金保険料の特例免除制度を利用することもできます。窓口で相談してみましょう。 また、退職者に第3号被保険者である配偶者がいる場合は、配偶者も同時に第1号被保険者への切り替え手続きを行い、保険料を納める必要があるので注意が必要です。再就職が決まったら、職場に年金手帳を提出し、厚生年金への加入手続きを行って、再び第2号被保険者となります。
第3号被保険者への切り替えには、「第2号被保険者である配偶者や両親に扶養されていること」「退職者の年収が130万円未満であること」などの条件を満たす必要があります。加入手続きは、第2号被保険者の勤務先を経由して年金事務所が行います。必要書類や提出方法は勤務先によって異なるため、担当者に確認しましょう。 再就職が決まったら、職場に年金手帳を提出し、厚生年金への加入手続きを行って、再び第2号被保険者となります。再就職でも扶養の範囲内で働くというケースであれば、第3号被保険者のままで新たに手続きを行う必要はありません。
退職後の「健康保険」は3種類から選んで手続きを進めよう
退職後の健康保険は通常、「A:それまで加入していた健康保険の任意継続被保険者制度を利用する」「B:国民健康保険に加入する」「C:家族の扶養に入る」の3パターンから選択し、変更手続きを行うことになります。
A:任意継続被保険者制度
退職後も在職中と同じ健康保険の被保険者資格を継続できる制度です。資格喪失日までに健康保険の被保険者期間が継続して2カ月以上あれば、2年間の期限付きで利用することができます。
・手続きの期間:退職日の翌日から20日以内
・手続きの場所:全国健康保険協会(協会けんぽ)など在職中に加入していた健康保険組合
・必要なもの:健康保険任意継続被保険者資格取得申請書、住民票、印鑑、1カ月分(退職日によっては2カ月分)の保険料など
任意継続被保険者制度を利用する場合は、それまでと同様に扶養家族の保険料はかかりませんが、自身の保険料が高くなるのはデメリットです。在職中には勤務先が保険料を半額負担してくれていましたが、退職後は全額を被保険者が支払うことになるため、上限は定められているものの、ほとんどのケースで保険料が上昇します。
B:国民健康保険
国民健康保険は各市町村が運営する健康保険制度で、組織に属さない自営業者などが多く加入しています。
・手続きの期間:退職日の翌日から14日以内(遅れてしまっても手続きは可能ですが、保険料は退職日翌日までさかのぼって支払う必要があります)
・手続きの場所:市区町村役所・役場の国民健康保険担当窓口
・必要なもの:健康保険の資格喪失日が記載された証明書(健康保険被保険者資格喪失証明書、退職証明書、離職票など)、各市町村で定められた届出書、印鑑など
保険料の額や納付方法は自治体ごとに異なるので、担当窓口に問い合わせましょう。退職者に扶養家族がいる場合は、国民健康保険に切り替えると扶養から外れて個々に保険料がかかってしまうため、任意継続被保険者制度を利用した場合との負担額を比較して判断することをお勧めします。
C:家族の扶養に入る
「年収130万円未満」「被保険者に生計を維持されている3親等以内の親族」などの条件を満たせば、配偶者や両親などの家族が加入している健康保険の被扶養者になることも可能です。手続きは、被保険者である家族の勤務先を経由して保険者に届け出ます。独自の要件や提出書類が設けられている場合もあるため、当該の保険者(健康保険組合、全国健康保険協会など)に問い合わせて確認しましょう。被扶養者であれば保険料は免除されます。再就職後も、扶養の範囲内で働く場合は切り替え手続きの必要はありありません。
転職活動中は「失業手当」を受け取ろう
在職中に加入していた雇用保険により、失業期間に失業手当を受け取ることができます。失業手当を受給できるかどうかは、退職後に転職活動をする人にとって、活動期間中の収入を左右する重要なポイントになります。失業手当を受け取るために必要な条件を確認し、早めにハローワークで手続きをしましょう。 失業手当を受給するためには、「積極的に働く意思を持ちながら失業状態である」「退職日以前の2年間に雇用保険加入期間が通算12カ月以上ある」「ハローワークに求職の申し込みをしている」という3つの条件を満たす必要があります。給付額や給付日数は、退職理由や被保険者期間、在職中の給与額などによって異なります。
自己都合や懲戒解雇など自らの意思や責任で退職した場合は給付制限があり、7日間の待機期間に加えて3カ月間は支給を受けることができません。ただし、自己都合であっても正当な理由があると認定された場合は、その限りではないこともあります。詳細はハローワークで確認してください。
◆失業手当受給の際の注意点
・受給期間中は4週間に1回、ハローワークを訪れて失業認定を受ける必要があります。
・すでに次の就職先が決まっていて、求職活動をする予定がない場合は、原則として支給されません。
・手続きが遅れると、受給開始日が遅れるうえ、受給できる期間に限度があるため給付日数満額を受け取れない可能性もあります。離職票を受け取ったら、早めに手続きしましょう。
◆早めに再就職が決まったら「再就職手当」を受け取ろう
失業手当の受給資格がある人が、給付日数を残して再就職した場合は、再就職手当が支給されます。「失業手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること」「7日間の待機期間満了後(自己都合退職などで給付制限がある場合は、さらに1カ月経過後)に決まった就職であること」「常用雇用であること」などの条件を満たしていれば、残っている給付額の50%ほどを受け取ることができます。 自己都合による退職の場合、失業手当の受給は3カ月後以降になりますが、再就職手当はそれ以前であっても受け取ることが可能なので、再就職先が決まったらハローワークで手続きをしましょう。 また、ハローワークや人材紹介会社を利用して再就職が決まった場合であれば、自己都合退職などで給付制限がある人も、例外として7日間の待機期間満了後に受給対象となります。再就職手当の受給額などは毎年改定される可能性があるため、詳細はハローワークのウェブサイトなどで確認しましょう。
税金(住民税、所得税)について知っておきたいこと
◆「住民税」は退職時期によって支払い方法が異なります
住民税は後払いのシステムです。1~12月までの1年間の所得に応じて決定された税額を、翌年の6月から翌々年の5月にかけて納める仕組みになっています。在職中は給与から自動的に天引きされていますが、退職すると支払いの区切りである5月までの残額を、「退職する職場で最終給与から一括で天引き」「役所から送付される納税通知書に従って分割して自分で支払い」「転職先の職場で給与から天引き」のいずれかの方法で納めることになります。どの方法になるかは退職や再就職の時期によって異なるので注意しましょう。
◆余分に支払った「所得税」は、年末調整か確定申告で還付を受けましょう
所得税は、想定される1年間の総収入を月割りにして、あらかじめ源泉徴収されています。退職後に1カ月以上の失業期間があるなどして年収が下がると、所得税を余分に支払ったことになり、余剰分は返してもらうことができます。余剰分の還付方法のパターンは、以下の2つです。
1.年内に再就職した場合
再就職先の職場で、12月に年末調整を行います。職場に源泉徴収票や控除証明書などの必要書類を提出することで手続きを代行してもらえるため、自分で手続きする必要はありません。
2.年内に再就職しなかった場合、年末に再就職して年末調整に間に合わなかった場合
翌年3月15日までの確定申告時期に、税務署で確定申告を行います(郵送、e-Taxも可)。確定申告書に加えて、源泉徴収票、生命保険や医療費などの控除証明書、印鑑などが必要になるので用意しておきましょう。確定申告は自分で行わなければならないため、不安な場合は税務署の相談コーナーを利用することをお勧めします。
転職・復職に悩んだら、まずはマイナビ看護師にご相談ください。
業界を熟知したキャリアアドバイザーと一緒に、
理想の転職を叶えましょう!
転職・復職に悩んだら、
まずはマイナビ看護師にご相談ください。
業界を熟知したキャリアアドバイザーと一緒に、理想の転職を叶えましょう!
Related article
Ranking
New arrival・Featured
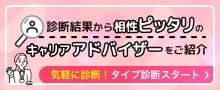
看護師のタイプ診断
簡単2ステップで、あなたのタイプを診断しあなたと相性ピッタリのキャリアアドバイザーをご紹介します!

看護師のお仕事マッチング診断
好みの求人を選んでいただくだけで、あなたのご希望にぴったり合う求人をご紹介します!

看護師の年収診断
今の年収は適正?看護師さんのための年収診断ツールです。

看護師の年収調査
周りの看護師の年収はいくらくらい?!他の職業との比較や年収診断も可能です。

はじめての転職
ささいな悩み・不安もお気軽に!まずは看護師専門キャリアアドバイザーに、相談してみませんか?

現役看護部長
おりんのお悩み相談室
現役看護部長の行徳輪子さんが、看護師さんの仕事の悩みにお答えします。

お悩みQ&A
周りには相談しづらい転職の疑問・お悩みに、スペシャリストがお答えします。
転職・復職に悩んだら、
まずはマイナビ看護師にご相談ください。