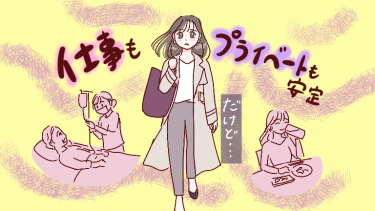病院は、想定外の救命活動が必要になる事態が起こりうる場所です。しかし、緊急事態が発生したときに、直接「救命活動が必要な患者が発生した」などと伝えると、患者さんや利用者さんが不安を感じます。そのため、病院内では想定外の救命活動が必要な患者さんを発見したときには、「コードブルー」を伝え、医師や看護師を招集するのが一般的です。
この記事では看護師の方に向けて、コードブルーの意味や発生したときの流れ、緊急時に対応する能力を身に付ける方法を解説します。看護師として予測できない事態でも冷静に対応したい方は、この記事を参考にしてください。
コードブルーとは?
コードブルーとは、病院内で想定外の救命活動が必要になったときに、医師・看護師をはじめとした病院内職員の皆さんを呼び出すための緊急コールです。スタットコール・コール救急などと呼ばれることもあり、病院によって名称は異なります。
コードブルーなどの緊急コールは、もともとはアメリカを発祥として作られた仕組みです。病院内の患者さんがパニックに陥らないよう、隠語を用いることで、緊急事態発生をスムーズに情報共有できるようになっています。しかし、医療ドラマ「コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命」のタイトルに採用されたことで、医療関係者以外にも名称が一般に知られるようになりました。
(出典:フジテレビ「コード・ブルー」)
コードブルーが発生する状況として多いのは、患者さんの容体が急変し心肺停止状態に陥っているなど、一刻も早く蘇生処置を行わなければならないケースです。
蘇生処置には多くの人手を要するため、放送を聞いた医師・看護師の皆さんは、直ちに現場にかけつける必要があります。一方、病院によっては、人員過多による混乱を防ぎ、迅速に対応できるよう、コードブルーに対応するチームをあらかじめ決めているケースもあります。
コードブルーが発生したときの流れ
コードブルーが発生したときの対処の流れは、状況や患者さんの容体、および病院によって異なります。以下では、呼びかけに反応がない心肺停止状態の患者さんを発見した場合を想定し、以下の4つのステップを紹介します。
| (1) | コードブルーをコールし、救命器具の手配を依頼する |
|---|
| (2) |
患者さんの気道を確保し、呼吸の有無・頸動脈の拍動を確認する 呼吸・頸動脈の拍動がない、あるいは呼吸が正常でない場合、直ちに胸骨圧迫・人工呼吸などの一次救命処置を行う |
|---|
| (3) |
応援にかけつけた医師・看護師の皆さんとともに役割分担をする 現場リーダーの指示のもと、救命器具を用いた二次救命処置を行う |
|---|
| (4) | 蘇生処置終了後、インシデントレポートの記録・報告や、患者さんのご家族への対応などを行う |
|---|
コードブルーの現場を発見した場合、看護師の役割は、まずは緊急コールを通して救命活動に必要な人員をなるべく多く集めることです。続いて、患者さんの状況を踏まえて的確な一次救命処置・二次救命処置を行い、最善を尽くして患者さんの蘇生を目指します。
救命救急処置の種類
救命活動には一次救命処置と二次救命処置があります。
- 一次救命処置(BLS)
専門的な器具・薬品などを使わない蘇生処置であり、気道確保・人工呼吸・胸骨圧迫などが挙げられます。コードブルー発生後、まだ救命器具が手元に届かない状況など、病院内でも一次救命処置を要するタイミングがあります。 - 二次救命処置(ACLS)
専門的な救命器具を使って行う蘇生処置であり、点滴セット・挿管セット・除細動器・薬剤などを用いて、医師・看護師が患者さんの状況を踏まえて処置を行います。
救命の最後の砦とも言われ、蘇生に関わる多くの医師・看護師の皆さんにとって不可欠な知識・技術といえます。
コードブルーの現場では、通常一次救命処置が二次救命処置用の器具の到着までに行われます。したがって、看護師は双方の救命処置に関する技術を身に付けておく必要があります。
コードブルー以外の緊急コールの種類

病院内で緊急事態が起こったときの緊急コールには、コードブルー以外にもさまざまな種類があります。代表的な緊急コールとして、コードホワイト・コードオレンジについて解説します。なお、病院により、採用されているものや意味合いは異なる場合もあります。
| コードホワイト |
|---|
| 病院内で暴言・暴力などの脅威が発生したことを示す緊急コードです。具体的には、患者さんやご家族によるスタッフへの暴言や、不審者が侵入し暴れている状況などのトラブルが想定されます。
コードホワイトが発生すると、警備員などが現場にかけつけ、暴言・暴力の発生源である人物を取り押さえます。病院によっては、身体の大きな看護師などが対応にあたることもあります。 |
| コードオレンジ |
|---|
| 災害発生を知らせるものです。 災害の種類や規模によっては、多数の傷病者が発生する可能性があります。 傷病者の受け入れが必要な場合、病院に空きベッドを作るなどの受け入れ体勢を確保したうえで、搬送された傷病者に対するトリアージ・救命活動などを行う必要があります。 |
ほかにも、病院によっては以下のような緊急コールが使われています。
| コードイエロー | 緊急で患者さんの搬送依頼があったことを知らせる |
|---|---|
| コードピンク | 病院内で乳児などの誘拐事件が起きたことを知らせる |
| コードレッド | 火災発生を知らせる |
| コードグリーン | テロの発生を知らせる |
どんなときも的確な対応ができるよう、看護師の働く病院における緊急コールの種類や発生時の対応方針をおさらいしておきましょう。
■関連記事
トリアージとは? JTAS法とSTART法の違いやトリアージの分類を解説
コードブルー訓練の必要性

コードブルーが発生した際に適切な行動を取るために、病院では定期的にコールが発生した際の対応を確認する訓練が行われます。コードブルー研修としては、以下のような事例があります。
- コードブルー発生時の手順について、院長による講評を挟みながら、複数回セッションを繰り返してロールプレイする
- 実際にコードブルーが発生した際の医師・看護師の皆さんの行動を振り返り、今後に向けた対応を検討する会議を設ける
慣れない環境においては、緊張や不安から冷静な対応ができなくなることがあります。コードブルー発生時にも落ち着いて行動できるよう、定期的な研修やケーススタディには積極的に参加し、自身の理解を確認することが重要です。
緊急時の対応を身に付けるには?

コードブルーなどの緊急時に焦らず対応する手段としては、救命活動の経験をより多く積むことが効果的です。看護師が救命活動に積極的に携わるキャリアステップの1つに、救急看護師の仕事があります。
救急看護師とは、文字通り救命活動が必要な人々に適切な救急看護を実践する仕事です。さらに、救急看護に必要な組織体制・救命器具などの調整・管理や、周囲への教育指導、看護研究、医療政策への参画など、幅広い業務を経験できます。患者さんの生命に関わる緊迫した状況に向き合うことが多い仕事であるため、救急看護師には的確な判断力や、専門的な知識・技術、ストレス耐性が必要となります。
救急看護師の働く場は、主に急患センターや救命救急センターなどの救急医療施設です。一方、ドクターヘリに同乗するフライトナースや、災害現場における救急隊員としての役割を担うこともあり、活躍の場は多岐にわたります。
(出典:一般社団法人日本救急看護学会「救急看護とは」)
■関連記事
DMATとは? 任務・活動事例・なり方・求められるスキルを解説
クリティカルケア分野の認定看護師とは
救急看護分野のスキルを向上し、専門性を伸ばす方法の1つに、クリティカルケア分野の認定看護師資格取得が挙げられます。
特定の分野に熟練していることを示すステップアップ資格として、認定看護師資格があります。認定看護師とは、看護師として5年以上の実務経験を持ち、日本看護協会が定める認定看護師教育を修め、認定看護師認定審査に合格することで取得できる資格です。
認定看護師には19種の認定看護分野があります。なかでも、クリティカルケア分野(旧:救急看護・集中ケア分野)の認定看護師は、救命活動を要する患者さんや、集中治療が必要な重症の患者さんなどに対応する高い専門性を証明する資格です。
緊急時に迅速な判断と初期対応を行う能力を身に付けたい看護師の方は、クリティカルケア分野の認定看護師の資格取得に挑戦してみましょう。
(出典:公益社団法人日本看護学会「認定看護師」)
(出典:公益社団法人大阪府看護協会「クリティカルケア認定看護師教育課程」)
■関連記事
まとめ
コードブルーが発生した際には、患者さんの状況を冷静に観察したうえで、適切な処置を行うことが重要です。迅速かつ的確に救命活動を行うためには、定期研修などの訓練に加え、救急看護師としての経験や、クリティカルケア分野の認定看護師資格取得などが効果的です。
救急看護師やクリティカルケア分野の認定看護師に興味のある方は、ぜひマイナビ看護師にご相談ください。看護業界に精通したキャリアアドバイザーが、ご希望に即したキャリアステップや求人情報についてご紹介いたします。
※当記事は2024年2月時点の情報をもとに作成しています

-375x211.jpg)