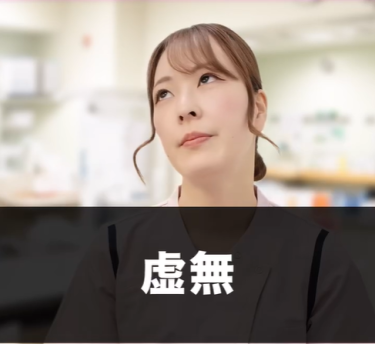災害大国、日本。2024年1月に起きた能登半島沖の地震では、多くの人が避難所生活を余儀なくされ、現在も1,700人を上回る人が1次避難所で過ごすなど、厳しい状況が続いています。そんな一変した生活に寄り添い、人々の健康を守るために被災地に派遣された災害支援ナース。
今回は実際に能登半島地震で災害支援ナースの統括リーダーとして活動された、宮城大学看護学群・講師の勝沼志保里さんにインタビュー。能登の現状を踏まえつつ、改めて現代における災害看護の役割とその重要性に迫ります。
被災者の健康管理や、避難所の運営サポート。被災者の生活を支える災害支援ナース
.jpeg)
勝沼さんは、能登半島地震発生後、県外の2次避難所に入るまで一時的に被災者を受け入れる1.5次避難所に、災害支援ナースとして派遣されました。当時の避難所の環境について、こう振り返ります。
勝沼さん(以下、敬称略):東日本大震災のとき、多くの避難所では、仕切りもなく区画整理がされておらず、ブルーシートの上に毛布で寝る(雑魚寝の状態)といった状況でした。ただ今回、私が派遣された1.5次避難所には、各世帯にテントが張られ、簡易的なベッドもあり、ライフラインの整備や食事の提供も十分にありました。東日本大震災のときに足りなかったハード面の課題は改善されつつあると感じています。

――東日本大震災を機に、避難所の環境整備が進んだのですね。その中で、災害支援ナースはどのような役割を担うのでしょうか?
勝沼:基本的に外部支援者として派遣されるため、被災された方々の体温・血圧測定や健康状態の観察のほか、避難所で困りごとがないか話を聞きつつ、現地に住む保健師や看護師を中心とした組織運営のサポートが中心です。ただ避難所によっては、現地の保健師や看護師も被災して運営に回れなかったり、そもそも過疎地でもともと看護師不足だったりしてマンパワーが足りず、災害支援ナースが組織運営の中心を担うこともあります。
――運営者が足りないケースもあるんですね……。運営者は具体的にどのような役割を担うのでしょうか?
勝沼:災害支援ナースのシフトや看るべき避難者の割り当て、緊急時の指示出しなどがメインです。本来は、震災発生直後から被災状況や住民の健康状態が把握できている人に担当してもらう形が理想ですが、今回の派遣では、避難所で災害支援ナース全体を管理している石川県看護協会のフロアマネージャーのもと、私が統括リーダーとなり、災害支援ナースの指揮系統整備などに携わりました。
――避難所以外に、災害支援ナースが派遣されることはありますか?
勝沼:現地の病院に派遣されることもあります。ただ病院は避難所とは違い、日頃から組織運営や指揮系統が整備されているため、災害支援ナースが運営に携わることはほとんどありません。災害支援ナースが病棟に派遣された場合、各病棟の医師や看護師からの指示を受けつつ看護します。被災地ですと、その組織運営をゼロから構築していかなければなりません。
――災害直後に派遣される医療チーム「DMAT(Disaster Medical Assistance Team)」にも看護師はいますよね。災害支援ナースとはどのような役割の違いがあるのでしょうか?
勝沼:DMATは、多くは被災地の病院もしくは空港などに設営した臨時医療施設に傷病者を集めて医療を提供するため、看護師の役割は医療補助です。災害支援ナースも部分的に医療補助に入りますが、基本的には被災された方々の生活を支え、健康を維持・サポートする役割が中心となります。
災害支援ナースが語る、避難所のリアルと災害支援の「見えない問題」
.jpg)
能登半島地震で災害支援ナースの統括リーダーとして活動した勝沼さん。1.5次避難所ではどのような看護が行なわれ、またどのような課題が見えたのでしょうか?
避難者の多くは単独世帯の高齢者
――1次避難所や1.5次避難所には、具体的にどのような方が避難されていたのでしょうか?
勝沼:当時、1次避難所には、家が倒壊して自主避難が困難になった方々が、1.5次避難所には2次避難所へ移動する予定で250人前後の避難者がいました。1.5次避難所にいた方のほとんどが単独世帯の高齢者でしたね。ただ、高齢者といっても、持病で継続的な投薬が必要な方、認知症が進んでいる方、感染症によって発熱している方など、抱えている症状はさまざまでしたね。
――病院のように必要な設備がない場所で、あらゆる症状の患者さんを看護するのは大変そうですね……。
勝沼:避難所に要介護者を優先に搬送させるスペースがあり、そこにDMATが常駐していました。感染症や重度の褥瘡によって医療提供が必要と判断された方は、彼らが対応していたんです。災害支援ナースが主に対応していたのは、基本的に健康だけど投薬管理が必要な方、認知症が進んでいる方々でした。投薬管理は、薬剤師が内服カレンダーを作り、看護師が内服の確認をしていました。認知症で徘徊してしまう方には、被災状況をお伝えして理解してもらうのは難しいため、テントを看護師の窓口近くに移動させて見守りつつ、いつでも話し相手になれるような環境を整えました。

――患者さんの症状によって役割分担がされていたんですね。被災された方の中に、現地で働く看護師さんはいましたか?
勝沼:私が派遣された時期には、現地の看護師さんで被災した方はいませんでした。ただ東日本大震災のときは、自身も被災者で家族が行方不明であるにも関わらず、看護師として支援を続けていた方が大勢いましたね。心も体もかなり疲労しているはずなのに、弱音を吐かず仕事を続けていました。
――被災者当事者でも働いている看護師さん……。きっと、心の中はつらい気持ちでいっぱいだったと思います。
勝沼:そうですね。ただ、緊張感で心が張り詰めている状態の人に「いまは仕事のことは考えず、しっかり休んでください」と伝えても、難しいだろうなとも思っていました。被災した看護師さんには、つらいことを考えず、何かに没頭する時間が必要だと思うんです。無理に仕事を奪ってしまうことで「自分には役割がない」と捉えられてしまう怖さもあったので、「3時間だけ、ここは私が代わります」と伝えて、短い時間で休憩を取ってもらうようにしていました。
浮き彫りになった、災害支援の「見えない問題」
――お話を伺っていると、避難所として最大限に機能しているように感じます。課題は何かありましたか?
勝沼:一つは、褥瘡の問題が挙げられます。避難生活では、ほとんどの高齢者が外出することなく座っているため、通常では発生しにくい親指の裏に褥瘡ができてしまった方がいました。まさかそんなところに褥瘡ができるとは思っていなかったのでびっくりしたのを覚えています。特に認知症が進んでいる高齢者の場合、自分の体の状況を正確に訴えられないことが多いため、災害時はより丁寧に話を聞いて健康状態を把握する必要があると改めて実感しましたね。
――他にはどのような課題が挙げられますか?
勝沼:テントの縁につまずき転倒しないための予防策や、炊き出しに来ていただく方に向けた、献立の呼びかけなども課題として挙げられます。特に炊き出しに関しては、元気を出してほしいと食事を振る舞ってくださった方がいたのですが、高齢者が多い避難所だと、体調や口に合わないという声が届きまして……。炊き出しに来てくださること自体は、非常にありがたいことなのですが、多くの人が食べられるものを作っていただくよう、炊き出しの具体的なガイドラインを作成するのも大切かなと感じています。
――特に大変だったことはありますか?
勝沼:災害支援に入るまでのシステムや、運営の指揮統制、情報共有の方法が十分ではなかったなと感じています。私の班は、派遣した初日から夜勤続行になった災害支援ナースが睡眠時間を削ってマンパワーの不足を補わないといけない状況でした。また前の支援チームが帰る時間が迫っていたこともあり、限られた時間で引き継ぎをしなければならず、情報収集にも苦労しました。オンライン上に各派遣チームの活動報告がタイムリーに閲覧できるシステムがあれば、情報共有がよりスムーズになり、より適切な看護の提供につながるのかなと思います。
災害看護は、看護職の専門性が最も発揮できる分野

東日本大震災、能登半島地震など地震による災害が多い日本において、看護師は重要なカギを握るはず。勝沼さんも、今後起こり得る災害に向けて、看護師が備えるべきことについて語ります。
勝沼:災害時、災害支援ナースを含め、全看護師は普段と違う環境下で活動しなければなりません。思い通りにはいかない歯痒さはあります。一方で、人々の生活が壊れ、健康に不調がおきている環境は、看護師本来のスキルを発揮できる場所だとも思っています。だからこそ日本の看護師全員は、来るべき災害に備えて、どういう状況でも対応できるようになるスキルが必要でしょう。
――きっとこの記事を読んで災害支援ナースを目指す人もいるはずです。勝沼さんが考える災害支援ナースとして求められるスキルや心構えを聞かせてください。
勝沼:災害時は、普段とは異なる医師、看護師、薬剤師、患者さんと関わるため、多様な人たちに関われるコミュニケーションスキルが求められると思っています。また、自分の力を過信せず、できることをできるだけやるという心構えも大切でしょう。過信は良くないですが、日頃自分が患者さんと向き合って培ってきたことは信じてほしいです。どんなに些細なことでも被災者のためにできたのであれば、それはできたこととして認めてもいいと思います。

――災害看護は、できることを見つけてやり抜くことが大切なんですね。勝沼さんがそう感じるようになったきっかけは?
勝沼:東日本大震災のときの話なのですが、避難所で70代の高齢の男性と話す機会がありました。見た目も元気で健康状態も悪くなかったのですが、お話聞くと津波で奥様を亡くしているとのこと。自分が助けてあげられなかったことをすごく悔やんでいて、お葬式に使う遺影も「アルバムを開くのが怖くて決められない」とおっしゃっていました。
――とてもつらいお話ですね……。
勝沼:私は何かできないかと考え、一緒にアルバムを見て写真を選ぶことにしました。1枚いい写真があったので「これにしませんか?」と伝えると、その方は安心して笑顔を見せてくださいました。そのとき、私は彼の明日につながる手助けができたと感じましたね。関わった時間は決して長くありませんでしたが、誰かのためにできることを見つけて、行動することがその人の未来をつくるきっかけになるとわかったんです。
――素敵な話をありがとうございました。最後に、災害支援ナースを目指す人にメッセージをお願いいたします。
勝沼:看護師という仕事を続けている以上、避難所や病院で何もできない、役に立たないことは絶対ありません。災害支援ナースを目指す際は、過信しない一方で、自分には何かできることがあると信じる気持ちも併せて持ってほしいなと思います。ぜひ頑張ってください!
勝沼 志保里
公立大学法人宮城大学看護学群の講師。基礎看護学、災害看護学を専門分野とし、災害後長期に避難生活を送る循環器疾患をもつ人の体験や看護ケアの開発に向けた研究に取り組んでいる。2024年1月に起きた能登半島地震では、宮城県看護協会災害支援ナースとして派遣され統括リーダーとして活動した。
取材/内山直弥、企画・編集/藤田佳奈美
-

今話題のトラベルナース!短期間かつ高給与の求人が揃ってます!
-

転職先で給与アップしたい方へ★
年収500万円以上の高収入求人や応募のポイントをご紹介! -

人気の転職時期である4月に転職するメリットはたくさん!
-

働きながら綺麗になれる♪常に人気の美容クリニック求人をピックアップ!
-

企業でも看護師資格を活かして働けます!ワークライフバランス◎
-

シフト勤務の環境を変えたい方向けに、土日祝休みの求人をご紹介!
-

看護師さんの約半分は夜勤なしで勤務中!無理なく働ける夜勤なし(日勤のみ)求人をご紹介!
-768x432.jpg)