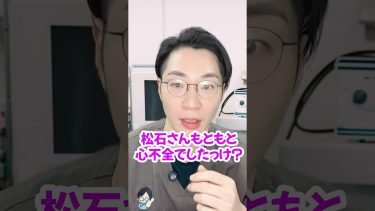SIRS(全身性炎症反応症候群)は、侵襲などによって引き起こされる全身性の炎症反応を指し、適切な対応を行わないと多臓器不全に至る可能性があります。その診断基準は成人と小児で異なり、症状の重症度や持続期間によって死亡リスクが高まる点が特徴です。また、SIRSは敗血症と混同されやすいですが、原因や診断基準が異なります。
当記事では、SIRSの定義・診断基準や敗血症との違い、診断基準の使用シーンと看護のポイントについて詳しく解説します。SIRSの適切な診断と早期治療は患者さんの予後に直結するため、基礎知識をしっかりと理解することが重要です。
【基礎知識】SIRSとは?
SIRSとは、侵襲に対して免疫細胞からサイトカインが過剰に分泌されて炎症性サイトカインが優位となり、全身性の炎症反応が現れる状態です。「Systemic Inflammatory Response Syndrome」の頭文字を取った略称で、日本語では「全身性炎症反応症候群」といいます。
SIRSの原因となる侵襲の種類は、感染・外傷・熱傷・膵炎や、手術のような臨床的侵襲などさまざまです。SIRSが重症化すると、ケミカルメディエーターや好中球、血液凝固因子が関与し、臓器障害や多臓器不全を引き起こすリスクが高まります。発症者の約30%がショックを引き起こすとされ、一見なんの症状もない患者さんでも、SIRSの基準を満たし、さらに要因を多く持っている場合は急変する危険性が高いので注意が必要です。
関連用語には、CARS(Compensated Anti-inflammatory Response Syndrome・代償性抗炎症反応症候群)があります。CARSとは、侵襲に対して免疫細胞から過剰分泌されたサイトカインのうち、抗炎症性サイトカインが優位となって起こる免疫抑制状態のことです。CARSになると免疫機能の低下によって感染症の併発が起こり、臓器障害を引き起こすと考えられています。
SIRSの診断基準:成人の場合
成人の場合におけるSIRSの診断基準は下記の通りです。
| 体温 | < 36℃または > 38℃ |
|---|---|
| 脈拍数 | 1分あたり90回以上 |
| 呼吸数 | 1分あたり20回以上またはPaCO2<32torr |
| 白血球数 | 1立方ミリメートルあたり4,000以下または12,000以上、もしくは10%以上の幼若好中球の出現 |
4つある診断基準のうち、2つ以上を満たす場合にSIRSと診断します。
SIRSの診断基準:小児の場合
小児の場合におけるSIRSの診断基準は、年齢によって異なります。
| 年齢 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0日~1週 | 1週~1か月 | 1か月~1歳 | 2~5歳 | 6~12歳 | 13~18歳 | |
| 深部体温 | < 36℃もしくは > 38.5℃ | |||||
| 脈拍数 (1分あたり) |
< 100回 または > 180回 |
< 100回 または > 180回 |
< 90回 または > 180回 |
>140回 | >130回 | >110回 |
| 呼吸数 (1分あたり) |
>50回 | >40回 | >34回 | >22回 | >18回 | >14回 |
| 白血球数 (1立方ミリメートルあたり) |
>34,000 | > 19,500 または <5,000 |
> 17,500 または <5,000 |
> 15,500 または <6,000 |
> 13,500 または <4,500 |
> 11,000 または <4,500 |
| もしくは10%を超える未熟好中球の出現 | ||||||
4つある診断基準のうち、2つ以上を満たす場合にSIRSと診断します。なお、小児の場合は深部体温と白血球数のいずれかは必須です。
SIRSの診断基準で分かる内容

SIRSの診断基準を使うことで、侵襲によって患者さんの身体にどの程度の炎症反応が発生しているかが分かります。SIRSは診断基準の項目を満たす数が多いほど死亡率が増加し、またSIRSが4日以上継続すると重症化するといわれています。特に2度目以降のSIRSは、最初のSIRSよりも状態が悪化しやすい傾向にあります。SIRSによる重症化や死亡を防ぐには、SIRSから早期離脱を図ることが重要です。SIRSを引き起こす侵襲(FIRST ATTACK)は、感染や外傷、熱傷、膵炎、手術、大量出血などさまざまです。
SIRSの診断基準の使用シーンと看護のポイント
SIRSの診断基準は、一般病棟・診療所や救急外来、集中治療室など多くの場所で使用されています。患者さんにSIRSの可能性があるときは診断基準をもとに評価し、基準を満たす場合は医師に報告しましょう。
SIRSと診断された患者さんに対しては、侵襲の原因である疾患や外傷を治療するとともに、炎症病態への対処を行います。抗炎症薬の投与や、血液浄化療法によるサイトカインの除去、呼吸・循環管理などが主な対処方法です。看護にあたってはバイタルサインや意識レベルを観察し、白血球数・CRP(C反応性タンパク)の持続高値、血小板数の減少傾向にも注意する必要があります。
SIRSと敗血症の違い

敗血症とは、感染に起因して制御できない宿主生体反応(免疫反応)が起こり、生命を脅かすほどの重篤な臓器障害がある状態のことです。また、敗血症のなかでも特に死亡率を上昇させるような重度の細胞障害や代謝異常が起こる状態は「敗血症性ショック」と呼ばれます。
SIRSと敗血症はどちらも過剰な免疫反応が関係していて、臓器障害を引き起こす点で共通しています。一方で原因となる侵襲は、SIRSは感染・外傷・熱傷・膵炎・手術など多岐にわたるのに対し、敗血症は細菌感染のみである点が違いです。SIRSの状態でかつ感染症を伴う場合、敗血症の可能性があります。ただし、すべての敗血症がSIRSの状態を呈するわけではありません。
2024年時点では下記のSOFAスコアを診断基準として、敗血症診断を行います。
| スコア | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 呼吸器 | PaO2/FiO2 (mmHg) |
≧400 | <400 | <300 | <200 かつ 呼吸補助 |
<100 かつ 呼吸補助 |
| 凝固能 | 血小板数 (×10の3乗/μL) |
≧150 | <150 | <100 | <50 | 20< |
| 肝臓 | ビリルビン値 (mg/dL) |
<1.2 | 1.2~1.9 | 2.0~5.9 | 6.0~11.9 | >12 |
| 循環器 | 平均動脈圧 (mmHg) |
MAP≧70 | MAP<70 | – | – | – |
| 投与量 (γ) |
– | – | DOA<5 or DOB |
DOA 5.1~15 or Ad ≦0.1 or NOA ≦0.1 |
DOA>15 or Ad>0.1 or NOA>0.1 |
|
| 中枢神経 | Glasgow Coma Scale | 15 | 13~14 | 10~12 | 6~9 | <6 |
| 腎機能 | 血漿クレアチニン値 (mg/dL) |
<1.2 | 1.2~1.9 | 2.0~3.4 | 3.5~4.9 | >5.0 |
| 尿量 (ml/日) |
– | – | – | <500 | <200 | |
感染症の罹患もしくは感染症疑いがあり、かつSOFAスコアのベースラインから合計2点以上の増加がある場合に、敗血症と診断します。
SIRSと敗血症の変遷
1992年に敗血症の定義としてSepsis-1が定められた際、敗血症は感染症を伴うSIRSとされていました。しかし、Sepsis-1の定義を用いると重篤な病態ではない場合にも敗血症と診断され、敗血症の特異性を説明できないことが問題点となります。
2001年には欧米の専門家がSepsis-2を定め、敗血症を「感染による全身症状を伴う症候」と定義し、24項目で構成される診断基準を作りました。しかしながら、Sepsis-2にも診断項目の多さや、科学的な診断基準が欠如しているという問題があり、あまり活用されない状況が続きます。
上記の経緯をたどり、2016年に改定された敗血症の定義が、2024年時点で使われているSepsis-3です。Sepsis-3では敗血症と敗血症性ショックの定義を作り、紹介した6つの指標からなる診断基準を定めています。
看護現場におけるSIRSの診断基準の使い方

看護現場におけるSIRSの診断基準の使い方を、2つの例で紹介します。
・例1
成人の患者さんを検査した結果、体温が37.2℃、脈拍数が1分あたり95回、呼吸数が1分あたり24回、白血球数が12,700/mm3だった。
脈拍数・呼吸数・白血球数の3項目で基準を満たすため、SIRSと判断できます。
・例2
成人の患者さんを検査した結果、体温が38.3℃、脈拍数が1分あたり82回、呼吸数が1分あたり17回、白血球数が8,600/mm3だった。
体温のみが基準を満たすため、SIRSではないと判断できます。ただし、脈拍数や呼吸数の数値が基準に近く、検査のタイミングによっては変化する可能性があるため観察が必要です。
まとめ
SIRSは侵襲に起因する全身性の炎症反応であり、適切な診断と治療が患者さんの生命を守る鍵となります。成人と小児では診断基準が異なり、特に小児の場合は年齢に応じた基準を用いる必要があります。また、SIRSが敗血症に移行するリスクを考慮し、早期離脱に向けた治療と継続的な観察が重要です。
当記事で解説した診断基準や看護ポイントを活用し、臨床現場での対応に役立ててください。看護師として働く中で、キャリアの見直しや転職を検討されている方は「マイナビ看護師」をぜひご活用ください。「マイナビ看護師」では、看護職専門のキャリアアドバイザーが、一人ひとりの状況や希望に合わせたキャリア支援を提供しています。
※当記事は2024年11月時点の情報をもとに作成しています
-

今話題のトラベルナース!短期間かつ高給与の求人が揃ってます!
-

転職先で給与アップしたい方へ★
年収500万円以上の高収入求人や応募のポイントをご紹介! -

人気の転職時期である4月に転職するメリットはたくさん!
-

働きながら綺麗になれる♪常に人気の美容クリニック求人をピックアップ!
-

企業でも看護師資格を活かして働けます!ワークライフバランス◎
-

シフト勤務の環境を変えたい方向けに、土日祝休みの求人をご紹介!
-

看護師さんの約半分は夜勤なしで勤務中!無理なく働ける夜勤なし(日勤のみ)求人をご紹介!