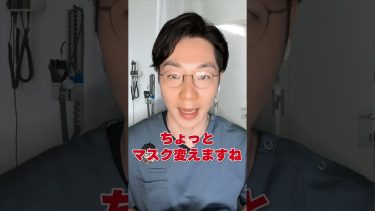何らかの原因によって腎臓の機能が低下すると、体に蓄積された老廃物や有害物質・水分が尿として排出されず、尿毒症や心不全をはじめとしたさまざまな疾患を招く可能性があります。尿毒症は重症化すると神経・精神症状が出て、最悪の場合、命にかかわることもあるため注意が必要です。
腎臓機能の低下が起きた際、本来であれば排せつされるはずだった老廃物や水分を除去するためには、「透析療法」が必要となります。透析療法は「人工透析」ともいわれ、名前の通り腎臓の本来の機能を人工的に代替する治療法です。
この記事では、人工透析の概要(血液透析・腹膜透析)から、透析患者さんに多い血液透析の手順、透析室で働く看護師のやりがいまで徹底解説しています。ぜひご覧ください。
人工透析とは
人工透析とは、腎臓の本来の機能を人工的に代替する医療行為のことです。腎臓の一部の働きを人工的な方法で補う治療法であり、「透析療法」や「透析」とも呼ばれます。
透析治療を受ける患者さんは、年々増加している傾向です。日本透析医学会によると、2022年末における新規透析導入患者数は39,683人でした。
(出典:一般社団法人 日本透析医学会「わが国の慢性透析療法の現況 第 1 章 2022年慢性透析療法の現況」)
加えて、過去6年間における慢性透析患者数の推移は下記のようになっています。
| 年数 | 慢性透析患者数 |
|---|---|
| 2017年 | 334,505人 |
| 2018年 | 339,841人 |
| 2019年 | 344,640人 |
| 2020年 | 347,671人 |
| 2021年 | 349,700人 |
| 2022年 | 347,474人 |
(出典:一般社団法人 日本透析医学会「わが国の慢性透析療法の現況 第 1 章 2021年慢性透析療法の現況」)
(出典:一般社団法人 日本透析医学会「わが国の慢性透析療法の現況 第 1 章 2022年慢性透析療法の現況」)
また、人工透析は「血液透析」と「腹膜透析」の2つに大別されます。ここからは、血液透析の仕組みと腹膜透析の仕組みをそれぞれ詳しく紹介します。
血液透析の仕組み
血液透析とは、全身の血液を体外に出して、ダイアライザという透析器の中で血液をろ過し、きれいにしてから再び体内に循環させる治療法です。英語で「Hemodialysis」と表現することから、「HD」と略されるケースもあります。週に2~3回行うことが基本で、一度の治療で約4~5時間を要します。
血液透析では、血液の出入口となるシャントを作成し、そこに脱血用と返血用の針を刺します。脱血用の針からは、1分間に約200mlの血液を取り出すことが可能です。体外に取り出した血液は、ポンプを経てダイアライザに送られ、ろ過されます。余分な老廃物などが除去されてきれいになった血液は、返血用の針を通して体内に戻されます。
2022年度の調査においては、日本で治療を受ける透析患者さんのうち約97%が血液透析を選択しており、末期腎不全の代表的な治療法といえるでしょう。
(出典:一般社団法人 日本透析医学会「わが国の慢性透析療法の現況 第 1 章 2022年慢性透析療法の現況」)
(出典:全腎協「血液透析の仕組み」)
腹膜透析の仕組み
腹膜透析とは、患者さんのお腹の中に透析液を入れて、腹膜を使って体内に蓄積された老廃物や水分を除去する治療法です。英語で「Peritoneal Dialysis」と表現することから、「PD」と略されるケースもあります。
腹膜透析は、さらに「CAPD(連続携行式腹膜透析)」と「APD(自動腹膜透析)」の2種類に分けられることが特徴です。
CAPD(連続携行式腹膜透析)は、生活リズムに合わせて1日に3~5回、患者さん本人もしくはその家族が透析液を交換する方法です。透析液の交換は、「バッグ交換」と呼ばれています。一方のAPD(自動腹膜透析)は、寝ている時間を利用してバッグ交換を自動的に行う方法です。
(出典:全腎協「腹膜透析の仕組みと種類」)
透析に関わる看護師の仕事内容

血液透析は、透析室という部屋で行われます。透析室で働く専門看護師は、透析室看護師や透析ナースと呼ばれ、一般病棟とは異なるさまざまな業務を担います。
透析室で働く看護師の主な仕事内容を確認しましょう。
透析に関する医療行為
透析準備は看護師の仕事です。また、病院によっては人工透析装置を使った一連の医療行為を、看護師が行うケースも少なくありません。
【具体例】
- 透析前のバイタルチェック、体重測定
- 内シャントへの穿刺
- 人工透析装置の状態観察
- シャント音、患部のチェック
- 透析終了後の抜針、止血
これらは、医師でなく看護師でも行える医療行為です。そのため、医師は診察や薬の処方などを担い、看護師が透析業務を担うという役割分担が主流です。
透析中の患者さんの看護
透析中は、体液量の変化に伴う体調変化が起こりやすくなります。注意深く様子を観察し、必要に応じた看護を行わなくてはなりません。
【具体例】
- バイタルチェック
- 透析結果を記録
- 顔色や気分が悪くなっていないか
- あくびが増えていないか(低血圧の可能性)
血圧低下が起こった場合には、基礎体重の適性値をチェックし、生理食塩水などの補液を投与するなどして対処します。
患者さんの健康管理
透析治療を受けている患者さんは、心不全や高血圧といった合併症を引き起こしやすいといわれています。合併症の発症を防ぎ健康を維持するため、日常的にさまざまなことに気を配らなくてはなりません。
| 聞き取り内容 |
|
|---|---|
| 指導内容 |
|
| 具体的な指導例 |
|
患者さんの健康や生活の質(QOL)を守るため、必要な生活指導を行うのも、看護師の仕事です。指導するべき内容は、患者さんにより異なります。聞き取った内容や血液の状態などから、指導内容を正しく判断しましょう。
看護記録業務
患者さんの状態や状況を看護記録として残すのも、看護師の大事な仕事です。外来において特に注意して記録・観察するべき事項は、以下の6つです。
| クラスター | 具体例 |
|---|---|
| 健康知覚・健康管理 |
|
| 栄養・代謝 |
|
| 認知・知覚 |
|
| 自己知覚・自己概念 |
|
| 排泄 |
|
| コーピング・ストレス |
|
記録を残すことは適切な治療計画・看護計画を立てる指標となります。また、スタッフ間でしっかり情報共有することも、チーム医療において重要なポイントです。
【看護師向け】血液透析の手順

前述の通り、近年では人工透析を導入する患者さんの数が年々増加しています。主に透析室勤務をする看護師さんの場合は、分野の認定を受けている場合や(腎不全看護認定看護師)、「透析技術認定士」資格を取得している方も少なくないでしょう。
透析を専門的に扱わない診療科勤務の看護師さんでも、血液透析治療を受ける患者さんと接する機会に備えて血液透析の手順やポイントを把握しておくことは、スキルアップにつながります。
そこで、看護師さんに向けて、医学書院の「透析ハンドブック 第5版」をもとに血液透析の手順を詳しく紹介します。
透析前準備
血液透析を行う際は、事前の準備が必須です。透析前準備では、下記のようなことを行います。
- 必要物品の準備
- プライミング・セッティング
- 体重測定
- 入室時の観察
- 透析条件指示の確認・設定
- 手指洗浄(患者さん・医療従事者ともに)
必要となる物品や設備の操作、条件設定については施設や患者さんによっても異なります。事前に各施設のマニュアルを確認することや、患者さんの状態をしっかり把握しておくことが欠かせません。
(出典:中外製薬「透析手順」)
(出典:医学書院「透析ハンドブック 第5版」)
透析開始操作
透析前準備が終わったら、透析開始操作を行います。基本的なプロセスは、下記の通りです。
●シャント肢の観察・確認
シャント血管の走行や感染の兆候、内出血の有無、シャント音の確認や、皮膚の厚さ・かたさ・たるみを触診して十分にシャント肢を観察します。
●穿刺
シャント肢の観察が終わったら、穿刺をします。穿刺部を消毒したのち、静脈側から実施しましょう。シャントを長期開存するためには、動脈側・静脈側の正確な穿刺が必要となるうえ、穿刺の失敗は患者さんに苦痛を与えかねないため、集中して行うことがポイントです。
●血液循環操作
穿刺を実施した後は、動脈側の穿刺針と血液回路を接続し、血液ポンプの血液流量を適切に設定・回転させます。このとき、脱血状態などに注意が必要です。その後、抗凝固剤を注入し、ダイアライザが薄い赤色になったら静脈側の穿刺針を接続します。定められた血液流量に合わせて血液ポンプを設定し、静脈圧の安定を確認できれば、透析を開始します。
上記はあくまでも透析開始操作の一般的な流れであり、具体的な透析設備の操作方法は施設によって異なることも覚えておきましょう。
(出典:中外製薬「透析手順」)
(出典:医学書院「透析ハンドブック 第5版」)
透析中の観察・記録
透析を開始した後は、治療が計画通りに進んでいるかの確認が必要です。患者さんの体の状態や透析設備の状況を十分に観察しましょう。それぞれで特に見ておくべきポイントは、下記の通りです。
●患者さんの体の状態
脈圧・血圧・体温・全身状態 など
●透析設備の状況
血流量・透析液濃度・静脈圧・抗凝固剤の注入速度・出血・穿刺針のゆるみやはずれ など
各項目は、1時間ごとの観察が推奨されています。
(出典:中外製薬「透析手順」)
(出典:医学書院「透析ハンドブック 第5版」)
透析終了操作
透析治療が終了に近づいたら、透析終了操作を始めます。終了時は、体外で循環された血液を安全に、かつ清潔に体内に戻すことが重要です。
透析終了時には、生理食塩水や消毒物品のほか、使い捨て手袋やゴミ袋、止血ベルトなどの衛生用品が主に必要となります。終了前には手洗いと患者さんの状態観察、検査、薬剤投与の有無の確認も忘れずに行いましょう。
(出典:中外製薬「透析手順」)
(出典:医学書院「透析ハンドブック 第5版」)
透析看護における観察項目

透析治療中の看護において、患者さんの観察は極めて重要です。治療前には患者さんの全身の状態や自己管理の程度、仕事や日常生活への影響などを確認します。透析中は、患者さんの表情や行動、不快感の表れとなる悪心、嘔吐、頭痛の有無をチェックします。
透析を続けている際に発生しやすい主な合併症は、以下の通りです。
【透析治療における主な合併症】
- ・高血圧・低血圧
高血圧は、塩分や水分の過剰摂取が原因で発生し、心臓病や脳卒中のリスクを高めます。
低血圧は、透析での除水による循環血液量の減少に加え血管収縮能の低下、心機能の障害によって起こるケースがあります。低血圧になると、めまいや全身の倦怠感を引き起こす可能性があります。 - 不均衡症候群
不均衡症候群は、透析導入期に起こりやすい合併症で、透析中や終了後12時間以内に腹痛、吐き気、嘔吐などの症状が現れます。これは、血液中の老廃物が除去される一方、脳内の老廃物は除去されにくく、体と脳との間に濃度差が生じるため、脳が水分を吸収してむくみ、脳圧が上昇することが原因です。体が透析に慣れてくると症状は軽減します。予防には、水分や塩分、タンパク質の制限を守ることで緩やかな透析を行うことや、透析時間の延長が有効です。 - 感染症
透析患者さんは免疫力が低下しやすく、穿刺部の感染や肺炎などさまざまな感染症にかかりやすくなります。 - 二次性副甲状腺機能障害
腎不全によりカルシウムとリンのバランスが崩れることで発生し、骨の脆弱化につながります。 - アミロイド骨関節症
長期間の透析によりアミロイドが蓄積し、関節痛やしびれなどを引き起こします。 - 高カリウム血症
カリウムが多く含まれる食品の摂取過多が原因で、手足のしびれや重い感じ、心機能障害を引き起こすことがあります。
(出典:一般社団法人 全国腎臓病協議会(全腎協)「合併症について」)
また、血液透析においてシャントのトラブルは、時に生命に関わる重大な事態を引き起こす恐れがあります。シャントの主な観察項目は以下の通りです。
- シャント音の確認
シャント部位に聴診器を当てたときに聞こえる音は、重要な観察指標です。通常、「ザーザー」といった低い音がするのが正常ですが、「ヒュンヒュン」といった高い音がする場合は狭窄を示唆していることがあります。 - スリルの確認
シャントの振動(スリル)は、血液が動脈から静脈に流れる際の物理的な振動です。スリルが感じられない場合、シャントの閉塞や分離が疑われ、適切な血流が確保されていない可能性があります。看護師によって定期的にチェックされる必要がありますが、患者さん自身にも毎日スリルの振動と強度を確認してもらうよう指導することが大切です。 - 皮膚の状態の確認
シャント部位は細菌が繁殖しやすく、発赤、熱感、かゆみ、かぶれなどを引き起こすことがあります。日々、皮膚の状態を観察し、異常を早期に発見できるようにすることが重要です。また、瘤やスチール症候群の兆候もなど併せて確認します。
透析で患者さんと関わる際に大切なこと

透析患者さんは、食事制限や水分制限など、日常生活に多くの制約があります。患者さんの生活を理解し、支えたいという思いが強い方は、透析看護の仕事を通して大きなやりがいを感じられるでしょう。
以下では、透析で患者さんと関わる際に大切なことを解説します。
患者さんと信頼関係を築く
長期にわたる透析治療は、患者さんにとって大きな負担となります。信頼できる医療スタッフの存在は、患者さんを精神的に支え、前向きな気持ちで治療を継続するうえで大きな力となります。
また、信頼関係があれば、患者さんは医師や看護師の指導やアドバイスを素直に受け入れやすくなります。適切な自己管理(食事療法、水分制限など)につながり、治療効果の向上や合併症の予防に貢献するでしょう。
そのためには、患者さんの言葉にじっくり耳を傾け、気持ちや状況を理解しようと努めることが大切です。また、治療内容や今後の見通し、合併症のリスクなどについて、分かりやすく丁寧に説明することも重要です。患者さんが疑問や不安な点を抱えていれば、納得いくまで説明し、安心感を持ってもらえるように心がけましょう。
シャントの取り扱いに注意する
透析看護において、シャントの取り扱いに注意することは、患者さんの生命線を守るために非常に重要です。シャントは、透析を行うために作られた血液の通り道であり、その管理が不十分であれば、透析治療が困難になるだけでなく、生命に関わる合併症を引き起こす可能性もあります。
そのために、狭窄・閉塞予防、感染予防、出血予防などをしっかり行いましょう。患者さん自身にもシャントの重要性や注意点について理解してもらい、自己管理をしっかりと促すことが大切です。
患者さんにとって最適な方法を考える
透析は、腎臓の機能が低下した患者さんにとって、生命維持に不可欠な治療法ですが、一方で、患者さんの生活に大きな影響を与えるものでもあります。1回の透析に4時間程度、週3回であれば週に15時間ほど拘束されるだけでなく、食事制限や水分制限、安静度の制限など、日常生活においてもさまざまな制限が必要となります。
そのため、看護師は、透析治療が患者さんの生活の質(QOL)を損なわないよう、医師、臨床工学技士、管理栄養士など、多職種と連携し、患者さん一人ひとりにとって最適な方法を常に考え、提案していくことが大切です。
たとえば、年齢、仕事、家族構成、趣味、生活習慣など、患者さんの生活背景を把握することで、透析が生活に与える影響を具体的にイメージできます。
透析室で働く看護師のやりがい・役割

透析室で働く看護師は、日々透析患者さんと関わっています。透析の準備業務、透析治療を受けている患者さんの看護・健康管理などの透析患者ケアが主な役割であり、専門性の高い業務に取り組むことも珍しくありません。
多くの専門的知識を要するものの、その分やりがいを感じられることも、透析室で働く看護師の大きな魅力です。
以下では、透析室で働く看護師のやりがい・役割を解説します。具体的には、「患者さんに頼られるような看護師になりたい」「専門的な知識を得たい」と考える看護師は、透析室での看護業務も向いているといえるでしょう。
専門知識を身に付けられる
透析室で働く看護師は、腎臓病の専門知識だけでなく、透析装置の操作、シャントの管理、合併症の対応など、幅広い専門知識と技術を習得できます。たとえば、透析患者さんは、さまざまな合併症(心不全、感染症、貧血など)のリスクを抱えています。合併症の早期発見・対応に必要な知識と技術を習得できるでしょう。また、ほかの医療従事者との関わりも多く、環境的にスキルアップしやすいです。
専門知識を身に付けることは、看護師としてのキャリアアップにつながるだけでなく、患者さんに質の高い看護を提供できるという大きなやりがいにもつながります。
患者さんと継続的に関われる
透析患者さんは、週に複数回、長期間にわたって透析治療を受ける必要があります。そのため、透析室で働く看護師は、患者さんと継続的に関わりやすく、信頼関係も築きやすい環境です。
透析患者さんにとって看護師は、治療のパートナーであるだけでなく、人生の伴走者でもあります。患者さんの人生に寄り添い、支えることは、大きなやりがいとなるでしょう。
透析室での看護の大変さ

透析室では、一般病棟では得られない専門的かつ特殊な知識が求められるため、就職後も学び続ける必要があります。透析に関する専門的な知識はもちろん、疾患や合併症の病態生理や日常生活での健康管理など、必要とされる知識は多岐にわたります。
複雑な透析装置の機械操作やシャントの穿刺などの技術面での成長も大切な課題です。実践を繰り返しながら身に付けていきましょう。
また患者さんと人間関係を築くことも、透析室看護の大変さの1つです。
透析室での勤務に向いている看護師の特徴

透析室看護師には、患者さんをしっかりと支えていきたい人やルーティンワーク・継続的な学びを苦に感じない方が向いています。
以下では、透析室での勤務に向いている看護師の特徴を5つ紹介します。
ルーティンワークが苦ではない人
外来や病院勤務と違い、透析室での仕事はルーティンワーク化され比較的単調です。決められた手順や時間を守りコツコツと働くことが好きな方や、日々の業務を効率的に行いながらも細かい点に気を配れる方に向いています。
患者さんと深く関わりたい人
透析治療は基本的に終わりがなく、一生続くものです。1回あたり約4時間の透析を数日おきに受けるため、患者さんと看護師との関わりは必然的に密になるでしょう。長期的に患者さんの健康をサポートしていきたい、深くコミュニケーションをとることが苦ではないという方に向いています。
キャリアアップしたい人
透析看護には、いくつかの専門資格が設けられています。透析室での勤務を続けることで、専門性の高い透析室看護師としてのキャリアアップが可能です。
専門的な知識や技術を身に付けたい人
透析医療は常に進歩しており、新しい透析装置や治療法が開発されています。透析室で働くことで、最新の医療技術に触れ、自己研鑽を続けることが可能です。
透析療法においては、血液透析・腹膜透析や、持続緩徐式血液濾過透析(CHDF)など、さまざまな透析療法の知識を深められます。透析装置においては、 最新の透析装置の操作方法やトラブルシューティングを学べるでしょう。
多職種と協働できる人
透析室では、医師、臨床工学技士、管理栄養士、医療ソーシャルワーカー、薬剤師など、さまざまな職種の専門家と連携してチーム医療を行います。
多職種と連携し、チーム医療を実践することで、はじめて患者さんにとって最適な医療を提供することが可能です。チームのために協力して頑張れる方は、透析室での勤務に向いているでしょう。
透析に携わる看護師の主な勤務場所

透析に携わる看護師の主な勤務場所として、病院とクリニックがあり、それぞれ特徴が異なります。
病院とクリニック、どちらを選ぶかは、ご自身のキャリアプランや希望するライフスタイル次第です。まずはどのような違いがあるのかを、確認してみましょう。
病院
病院は、入院患者用のベッドである「病床数」が20床以上ある医療機関です。
急性腎不全や心臓病などのリスクが高い疾患など、緊急性の高い透析が必要な患者さんが多く、重症度の高い患者さんの看護に携わることが多いです。病院によっては、夜勤やオンコールがある場合があります。
クリニック
クリニック(診療所)は、病床数が19床以下の医療機関です。通院での治療が大半で、基本的には血液透析のみを行っているケースが多いです。
基本的に夜勤がないので、体力的な負担が少なく、ワークライフバランスを保って働きやすいでしょう。また、患者さんとの関係を築きやすいのもメリットの1つです。
透析室看護師のスキルアップ資格

透析室勤務は、分野の専門的な知識が深く身につきます。勤務の中で得た知識とスキルを、資格認定という目に見える形で評価してもらい、看護師としてのスキルアップを目指しましょう。
ここでは透析室で働く看護師におすすめの資格を3つ紹介します。
慢性腎臓病療養指導看護師
慢性腎臓病療養指導看護師は、日本腎不全看護学会が慢性腎臓病の現場における看護ケアの質向上を目的として立ち上げた資格制度です。元々は透析療養法指導看護師という名称でしたが、平成15年より慢性腎臓病療養指導看護師(CKDLN)と呼ぶようになりました。
| 資格取得方法 |
|---|
|
受験資格を満たしたうえで、日本腎不全看護学会の公式ホームページから申し込みを行う。 【受験資格】
|
腎不全看護認定看護師
日本看護協会が定めた認定制度の1つで、腎不全看護領域に特化した専門的な知識と経験をもった看護師のことです。認定看護師教育基準カリキュラムに定められた座学や演習(合計時間数約800時間)を行ったうえでの受験となります。
| 資格取得方法 |
|---|
|
受験資格を満たしたうえで、日本看護協会の公式ホームページから申し込みを行う。 【受験資格】
|
(出典:公益社団法人 日本看護協会「認定看護師」)
透析技術認定士
透析技術認定士とは、医師の指導監督のもと透析装置の操作と管理を行う仕事をする人のことです。臨床工学技士と似ていますが、こちらは透析ケアに特化した資格です。
| 資格取得方法 |
|---|
|
受験資格を満たしたうえで、医療機器センターのホームページの専用フォームを通して申し込みを行う。 【受験資格】
|
まとめ
人工透析とは、腎臓の本来の機能を人工的に代替する医療行為のことであり、大きく「血液透析」と「腹膜透析」の2つに分けられます。日本の透析患者さんの多くは、血液透析(HD)で治療を受けている傾向です。
近年では、人工透析を導入する患者さんの数が年々増加していることから、透析に関する仕事の知識をもつ看護師の需要も高まることが予想されます。病院・クリニックといった医療機関で働く看護師さんで、スキルアップを目指しているのであれば、透析室での勤務を視野に入れてみてはいかがでしょうか。
透析室看護師を含むさまざまな求人情報を多数掲載する看護師転職サイト「マイナビ看護師」では、理想の条件を満たす求人を簡単に検索・チェックできます。転職を少しでも検討している看護師さんは、医療業界に精通したキャリアアドバイザーによる求人の紹介から応募先への条件交渉まで、幅広い転職支援を提供する「無料転職サポートサービス」をぜひご利用ください。
※当記事は2024年6月時点の情報をもとに作成しています
■関連記事
-

今話題のトラベルナース!短期間かつ高給与の求人が揃ってます!
-

転職先で給与アップしたい方へ★
年収500万円以上の高収入求人や応募のポイントをご紹介! -

人気の転職時期である4月に転職するメリットはたくさん!
-

働きながら綺麗になれる♪常に人気の美容クリニック求人をピックアップ!
-

企業でも看護師資格を活かして働けます!ワークライフバランス◎
-

シフト勤務の環境を変えたい方向けに、土日祝休みの求人をご紹介!
-

看護師さんの約半分は夜勤なしで勤務中!無理なく働ける夜勤なし(日勤のみ)求人をご紹介!