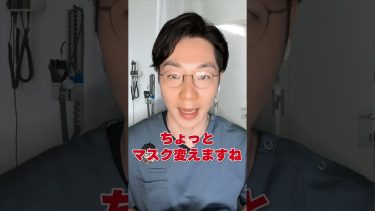看護師として活躍している方のなかには、災害医療について学んでいる方や災害医療の現場で活動することを考えている方もいるでしょう。また、災害医療への理解を深める中で、「EMIS」という言葉を見聞きすることもあるのではないでしょうか。
当記事では、災害医療の現場に不可欠なシステムである「EMIS」について、その概要と役割、開発の背景、災害時におけるEMISの機能やEMISが抱える課題を解説します。災害医療の現場でも冷静に行動できるよう、EMISに関する適切な知識を身につけましょう。
EMISとは?
EMIS(Emergency Medical Information System)とは、日本語で「広域災害救急医療情報システム」と表される、災害医療の現場に欠かせない情報システムを指します。
大規模災害発生時の死傷者を最小限に抑えるためには、被災地やその周辺地域における医療機関の稼働状況などの情報を自治体の垣根を越えて共有することが大切です。EMISは、被災地域に必要な医療・救護・看護を迅速かつ適切に提供するための情報を収集・集約・提供する目的で使用されています。
(出典:厚生労働省・広域災害救急医療情報センター「広域災害救急医療情報システム(EMIS)Emergency Medical Information System」)
なお、EMISは厚生労働省を筆頭に、47あるすべての都道府県や多くの医療機関、DMATなどの医療支援チームが主に利用しています。2018年4月時点における医療機関(病院・診療所)の登録率は93%と高く、消防本部や医師会、市区町村・保健所の登録も進んでいます。
(出典:厚生労働省「広域災害・救急医療情報システム(EMIS)概要について (株式会社 NTTデータ)」)
EMISが開発された背景
EMISが開発されたきっかけは、1995年1月に発生した「阪神淡路大震災」です。大規模地震のような大きな災害の発生時には、一般的に県庁や市役所などが調整・指示を行いますが、阪神淡路大震災ではこれらの機関も大きな被害を受けました。自治体と各医療機関、医療機関どうしの情報共有がうまくいかず、医療の現場が混乱する事態に陥りました。
被災地域の医療機関・医療従事者は最適な対応をしようとしましたが、患者さんが一部の医療機関に集中するといった医療の不均衡が発生した地域も少なくありません。また、施設の倒壊やライフラインの停止、医療資源の不足など、医療体制が麻痺し満足な医療行為・看護ケアを行えない医療機関に関する情報も十分に共有できませんでした。
このように、被災地域における医療情報が錯綜したことで、本来であれば防げた可能性が高い災害死は、阪神淡路大震災では500人を超えたといわれています。
(出典:日本赤十字社 和歌山医療センター「EMISとは…?」)
阪神淡路大震災の教訓から、EMISは災害発生時における都道府県・市区町村の枠を越えた迅速な医療情報共有を目的に開発されました。1996年に運用が開始されたEMISは、改良を重ねながら発展し、現在では被災地域に適切で迅速な医療提供に欠かせないシステムとなっています。
(出典:厚生労働省「広域災害・救急医療情報システム(EMIS)概要について (株式会社 NTTデータ)」)
災害時にEMISとともに活躍するDMATとは?

DMAT(Disaster Medical Assistance Team)は、大規模災害や多数の傷病者が発生した際に、急性期(おおむね48時間以内)から活動できる機動性を持った、専門的な訓練を受けた医療チームです。DMATは、医師や看護師、業務調整員などで構成されます。主に災害が起きた直後に派遣され、自衛隊や警察、消防と連携しながら、災害現場での医療提供や患者さんの搬送、病院支援など多岐にわたる任務を担います。
DMAT誕生のきっかけはEMIS(広域災害救急医療情報システム)と同様、1995年に発生した阪神淡路大震災です。医療の遅れによって救えるはずだった命が多数失われた震災の教訓を受け、2005年に厚生労働省の主導で「日本DMAT」が設立されました。
日常的には医療機関で通常業務を行いながら、発災時にはすぐに現場に駆けつけられるように訓練や準備を行っています。また発足以来、地震や事故などの大規模災害だけでなく、感染症のような公衆衛生上の危機など、国内での緊急事態で重要な役割を果たしてきました。現在では現場の医療だけでなく、病院の指揮下に入り医療行為を支援する病院支援や、想定される大地震で多数の重症患者が発生した際に、平時の救急医療レベルを提供するため、被災地の外に搬送する広域医療搬送など、機動性、専門性を生かした医療的支援を行います。
(出典:厚生労働省 DMAT事務局「DMATとは」)
■関連記事
DMATとは? 任務・活動事例・なり方・求められるスキルを解説
EMISとG-MISの違い

EMIS(広域災害救急医療情報システム)とG-MIS(新型コロナウイルス感染症医療機関等情報支援システム)は、どちらも医療支援を目的とした情報共有システムですが、その使用目的や機能には大きな違いがあります。以下では、EMISとG-MISの違いとG-MISのメリットを解説します。
G-MISとは?
G-MIS(Gathering Medical Information System on COVID-19)は、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、医療機関の稼働状況や医療資源の確保を支援するために構築されました。2020年に導入された比較的新しいシステムです。G-MISは、医療機関の入力情報をリアルタイムで自治体や国と共有し、病床数や医療スタッフの配置状況、必要な医療機器の不足を即座に把握できます。
G-MISは、医療提供体制を維持するための重要なツールです。たとえば、人工呼吸器や防護服など、必要な医療資材の不足が生じた場合、医療機関はG-MISを通じて迅速に支援を要請できます。感染が急速に拡大した場合でも、各自治体や国がタイムリーに対応し、医療崩壊を防ぐための対策を講じることが可能になります。
(出典:厚生労働省「EMIS(広域災害・救急医療情報システム)及びG-MIS(新型コロナウイルス感染症医療機関等情報支援システム)について」)
G-MISのメリット
G-MISの導入によって、国民・医療従事者・自治体それぞれに多くのメリットがあります。国民にとっては、病院の稼働状況が政府のポータルサイトを通じて可視化されるため、受診できる医療機関を迅速に見つけられるのがメリットです。医療従事者にとっては、必要情報の一元化により、日々の業務負担の軽減と、必要な支援が迅速に受けられる環境の整備が期待できます。
自治体のメリットは、リアルタイムで集約される病院や診療所からの情報をもとに、医療資源の配分や病床の確保など、適切な対応が可能となる点です。これにより、感染症対策の効果が向上し、医療提供体制の強化につながります。G-MISは、緊急時の対応力を高め、医療機関の効率的な運営を支援するシステムです。
(出典:厚生労働省「EMIS(広域災害・救急医療情報システム)及びG-MIS(新型コロナウイルス感染症医療機関等情報支援システム)について」)
災害時のEMISの役割

EMISは、災害時において重要な役割を果たすシステムです。その役割は主に「広域搬送」と「DMAT派遣」の2つに分けられます。災害急性期における医療支援を効率的かつ迅速に行うには、EMISによる医療情報の共有が不可欠です。以下では、それぞれの場面でEMISが果たす役割を解説します。
広域搬送
広域搬送は、災害発生時に重症患者を被災地域外の医療施設に移送するための仕組みです。大規模災害発生時、被災地内の医療施設だけでは対応しきれないケースが少なくありません。現地での治療が難しい患者さんの命をつなぐ希望となるのが、広域搬送です。
広域搬送の際には、各都道府県が事前に指定した「広域搬送拠点臨時医療施設(SCU)」が重要な役割を果たします。SCUは、患者さんの重症度に基づいてトリアージを行い、医療措置と搬送の要否を判断する場所です。搬送には、自治体・消防・自衛隊など複数の関係機関が連携するため、情報の共有と調整が欠かせません。EMISは、被災地域内の医療機関の稼働状況や患者さんの状態をリアルタイムで把握・共有し、適切な搬送先の決定を助けるツールです。
(出典:愛知医科大学「第9 トリアージ、治療、広域搬送」)
(出典:日赤和歌山 情報局「CSCATTT トランスポート(搬送)②」)
DMAT派遣
DMAT(災害派遣医療チーム)は、災害発生直後に被災地へ迅速に派遣される医療チームです。災害が発生すると、被災都道府県がEMISを通じて被害状況や医療ニーズを把握し、必要に応じてDMATの派遣要請を行います。派遣要請は、被災地の医療機関から出される場合もあれば、厚生労働省が緊急性を判断して直接行う場合もあります。
被災状況によっては、現場での活動と並行して避難中の被災者へ迅速に医療を提供しなければなりません。EMISを活用すれば、DMATが被災地の最新情報をもとに迅速に行動でき、災害発生直後の急性期における効果的な医療支援が可能となります。EMISとDMATの連携は、災害時における医療活動の中核を成し、多くの命を救うために欠かせない要素です。
(出典:厚生労働省 DMAT事務局「DMATとは」)
EMISを使って得られる情報

EMISからは、医療関係者だけでなく一般利用者も緊急時に必要な各種情報を迅速に入手できます。提供される情報は一般利用者向けと医療関係者向けで異なりますが、どちらも災害時の適切な対応が重要です。以下では、それぞれの情報の違いについて解説します。
一般利用者の場合
一般利用者がEMISを通じて得られる情報は、災害に対する基本的な知識や災害時の対処方法に関するものが中心です。以下のような情報が提供されています。
- 各都道府県の災害情報・警戒情報
- 登録医療機関検索機能(条件指定可)
- 救急医療に関する予備知識
- 災害時の対応マニュアルと事例
- 地震や火災などの災害に関する基本的な知識
- 全国行政機関の連絡先
- 災害救急に関するリンク集
これらの情報は、災害が発生した際に迅速に行動できるよう、誰でもEMISのホームページで確認できます。また、日常的に災害への備えをしておくためにも有用です。緊急時にスムーズな医療支援を受けられるよう、災害時に利用可能な医療機関情報などをあらかじめ確認しておくとよいでしょう。
(出典:厚生労働省「EMIS」)
医療関係者の場合
医療関係者向けに提供されるEMISの情報は、より専門的で災害医療情報に特化した内容です。システムにログインすると、次のような情報を入手・活用できます。
- 災害救急医療情報の登録・提供・集計・検索
- 災害発生時の速報配信
- DMATの派遣要請・活動状況の確認
- 各医療機関の稼働状況や医療資源の状況
- メーリングリストやメールマガジンによる情報共有
- 被災地から厚生労働省への通報・問い合わせ
- システム運用状態の切り替え機能
これらの機能により、医療関係者は災害発生時に迅速かつ適切な情報収集と対応が可能です。たとえば、被災地域の医療機関の稼働状況や医療体制を把握すれば、広域搬送の対象となる医療機関が迅速に患者受け入れ態勢を整えられます。
(出典:厚生労働省「EMIS」)
(出典:厚生労働省「広域災害・救急医療情報システム(EMIS)概要について」)
(出典:岡山県「広域災害救急医療情報システム(EMIS)入力マニュアル」)
医療関係者は、普段からEMIS操作法やデータの様式に慣れておくことが重要です。災害時に円滑にシステムを利用できるよう医療機関用のEMISアカウント登録を済ませておき、平常時から訓練や情報共有を徹底しておきましょう。
災害時のEMISの機能

災害時におけるEMISの機能には、主に次の3つがあります。
◆災害時におけるEMISの3つの機能
(1)EMIS基本機能
(2)DMAT管理機能
(3)医療搬送患者管理機能
(出典:東京都福祉保健局「広域災害救急医療情報システム(EMIS)について」)
ここでは、上記の3つの機能の概要や主な利用方法について解説します。各機能の役割や用途について確認し、EMISへの理解を深めましょう。
EMIS基本機能
EMIS基本機能とは、災害発生後における医療機関の被災状況や受け入れ患者の可否・受け入れ可能な患者数などの情報収集を行い、関係各所で共有するための機能です。EMIS基本機能は、主に次のような機能から構成されています。
◆EMIS基本機能の概要
| 機能 | 主な利用者 | 利用のしかた |
|---|---|---|
| 緊急時入力 | 医療機関 | 「倒壊状況」「ライフライン・サプライ状況(停電・断水・医療ガスの故障停止など)」「患者受診状況」「職員状況」のように、災害発生直後の医療機関における状況を入力します。 |
| 詳細入力 | 医療機関 | 災害発生後、医療機関の稼働状況をある程度把握できたころに詳細な情報を入力します。 |
| 統合地図ビューアー | 都道府県 | 医療機関をマッピングした地図と併せて、災害情報や医療機関の被害状況・詳細情報を確認できます。 |
| 医療機関等・支援状況モニター | 全関係者 | 医療ニーズや支援チームの手配状況を確認できます。 |
DMAT管理機能
DMAT管理機能とは、DMATの派遣要請・活動状況を管理し、DMATに関する情報を関係機関各所で共有するための機能を指します。
DMAT(Disaster Medical Assistance Team)は、災害発生後の急性期に医療活動できるようトレーニングを受けた医療チームのことです。医師や看護師などの医療職や事務職員から構成されており、被災地域での迅速かつ適切な医療ケアの提供に貢献しています。
(出典:厚生労働省 DMAT事務局「DMAT」とは)
■関連記事
DMATとは? 任務・活動事例・なり方・求められるスキルを解説
◆DMAT管理機能の概要
| 機能 | 主な利用者 | 利用のしかた |
|---|---|---|
| DMAT登録者管理 | DMAT・DMAT事務局 | DMATに所属している隊員の基本情報や資格情報、研修受講状況を登録・確認できます。 |
| 活動状況モニター | 都道府県 (行政機関) |
DMAT派遣要請や各チームの基本情報、活動状況、目的地・活動中の場所などの情報を確認できます。 |
医療搬送患者管理機能
医療搬送患者管理機能とは、医療搬送の対象となる患者さんや広域搬送を行う航空機の管理を行い、搬送先の医療機関やDMATなどと情報を共有するための機能を指します。
大規模災害が発生した場合、被災地域内では十分な医療が提供できないケースも少なくありません。重症の患者さんの場合は、被災地域外から派遣されたDMATや救護班が被災地域外の災害拠点病院などに救急搬送する必要があります。この一連の流れである「広域医療搬送」をサポートするのが、EMISの医療搬送患者管理機能です。
◆医療搬送患者管理機能の概要
| 機能 | 主な利用者 | 利用のしかた |
|---|---|---|
| 医療搬送患者モニター | DMAT | 搬送が必要な患者さんの情報や、搬送先の医療機関情報、搬送手段の登録・管理・確認ができます。 |
EMISの課題

EMISは1996年の運用開始以降、2016年の熊本地震や2018年の北海道胆振東部地震など、さまざまな災害発生現場で活用されてきました。EMISは災害発生時における迅速かつ適切な医療提供に大きく貢献してきましたが、活用の歴史の中で見えてきた課題もあります。
ここでは、今後改善が期待される2つの課題について解説します。課題のポイントや改善のために取り組むべきことを確認し、今後のEMIS利用や災害医療現場での活動に活かしましょう。
システム操作性についての課題
EMISが抱える課題の1つとして、「システム操作性の改善」が挙げられます。EMISは災害発生時において必要な情報を集約し整理できるメリットがある一方で、円滑な操作が難しいという声もありました。視認性やデザイン性も良好な状態とはいえないため、必要な情報をすぐに発見できないデメリットもあります。
今後はこれらの課題を解決するために、システムプログラムの見直しやインターフェース(視認性・デザイン性)の向上に対する取り組みの実施が期待されます。また、長期支援に向けた経時的な変化を確認する機能の搭載や、タブレット・スマートフォンのアプリ開発、オフライン操作を可能とする様式変更も検討されるでしょう。
(出典:厚生労働省・兵庫県災害医療センター「広域災害・救急医療情報システム(EMIS)の歴史と進歩、そして課題」)
操作者の習熟度についての課題
EMISは主に災害発生時という非常時に使用されるシステムであり、平時に関しては多忙な医療職や自治体職員はほぼ利用することがありません。また、災害発生時には必ずEMISを使用するDMATですら、使用頻度は半年に1回程度といわれています。システムの複雑さの改善も重要ですが、操作者の習熟度の向上もEMIS運用の大きな課題といえるでしょう。
操作者の習熟度向上に向けた取り組みとしては、研修会の開催など十分な研修体制の構築および、より多くの機関に対するEMIS操作法の普及活動などが挙げられます。個人で練習可能な「トレーニングモード」の搭載も検討されており、看護師も今後はEMISの知識・スキルの習得と災害への備えが求められると考えられます。
(出典:厚生労働省・兵庫県災害医療センター「広域災害・救急医療情報システム(EMIS)の歴史と進歩、そして課題」)
まとめ
EMISとは、災害発生時に被災地域の医療情報を集約し、その情報を活用して迅速かつ適切な医療を被災地域に提供するために開発された情報システムのことです。EMISにはさまざまな機能があり、1996年の運用開始以降多くの災害現場における救助活動に活用されてきました。
現在ではEMISが抱える課題の解消に向けた取り組みも行われており、今後は一般の看護師もEMISに関する知識・スキルを身につけることが求められると考えられます。知識・スキルを磨くために転職を検討している方は、看護業界に精通したキャリアアドバイザーが在籍する「マイナビ看護師」にぜひご相談ください。
※当記事は2024年8月時点の情報をもとに作成しています
-

今話題のトラベルナース!短期間かつ高給与の求人が揃ってます!
-

転職先で給与アップしたい方へ★
年収500万円以上の高収入求人や応募のポイントをご紹介! -

人気の転職時期である4月に転職するメリットはたくさん!
-

働きながら綺麗になれる♪常に人気の美容クリニック求人をピックアップ!
-

企業でも看護師資格を活かして働けます!ワークライフバランス◎
-

シフト勤務の環境を変えたい方向けに、土日祝休みの求人をご紹介!
-

看護師さんの約半分は夜勤なしで勤務中!無理なく働ける夜勤なし(日勤のみ)求人をご紹介!