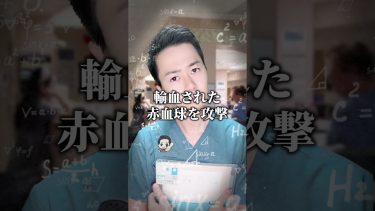「医療政策」という言葉を聞くと、多くの人が「自分が関われるような話ではない」と感じるかもしれません。でも、本当にそうでしょうか。私たちのまわりには、大きな夢に挑戦し、それを実現させ、日々がんばっている人もたくさんいます。たとえばーー。助産師から自身のキャリアをスタートさせ、その臨床経験を生かしながら、医療分野の政策提言に挑んでいる今村優子さんもその一人。ここでは、特定非営利活動法人日本医療政策機構(HGPI)でマネージャーを務める今村さんに、助産師としてのキャリアや現職のやりがい、魅力についてお話を伺ってみました。

日本医療政策機構 マネージャー 今村優子さん総合周産期母子医療センター愛育病院や育良クリニック(いずれも東京都)などで助産師として8年間の臨床経験を積み、イギリスに留学。シェフィールド大学にて公衆衛生学修士課程修了(Master of Public Health;MRH)。帰国後、2017年2月より日本医療政策機構に参画し、マネージャーとして医療および医療制度に関する世論調査、医療政策の提言などを行っている。
心から仕事を楽しみ、毎日がときめいていた臨床時代

助産師として現場に立っているときは、お産を介助したり、妊産婦さんと関わったりすることがとにかく楽しくて、毎日ときめいていました。育良クリニックでは、担当助産師制度が取り入れられていて、産前から産後1年までの継続的なケアができたのですが、それが大きなやりがいにもなっていましたね。長期的に妊産婦さんと関われるので、お互いに信頼関係が築きやすく、2人目以降の出産でご指名をいただいたこともあるんです。
新しい母親学級を立ち上げたのも、育良クリニック時代のことです。自然分娩をメインコンセプトとしている産院でしたので、そこに惹かれて来院する方も多くいらっしゃいましたが、中には自然分娩への理解が不十分だったり、お産に対して受け身だったりする方も、少なからずいらっしゃいました。それで「人生の一大イベントである出産だからこそ、十分な準備をして臨んでほしい」という思いが少しずつ膨らんでいき、妊娠34~36週限定の母親学級を企画することにしたんです。「産むぞクラス」と名付けられたその学級は、現在も続いており、1時間半かけて安産のコツや「助産師はいつでもどんなときでも、頼っていい存在である」ということを伝えています。
「産むぞクラス」の最大の特徴は、プログラムの最後に行う寸劇。後輩助産師が妊婦さん役、私が助産師役として出産の様子を熱演するのですが、助産師なので陣痛時の状態や呼吸の変化を細かく演じ分けられる、という点が好評でした。中には、感情移入して涙する参加者もいたくらい。おかげで、受講後は妊婦さんの意識が大きく変化し、「体力を付けるためにスクワットをはじめました」「寝る前に呼吸法の練習をしています」といった声がたくさん届くようになったんですよ。
女性の意識改革を助産師として手助けしたい

「産むぞクラス」の成功はもちろんうれしかったです。ただ、それはあくまで一つの病院に限定した取り組み。「もっと何かできることはないだろうか」と考えるうちに、今度は「学生から社会人までを対象に、より幅広く妊娠・出産に関する教育活動を展開し、女性の意識改革へつなげたい」と思うようになりました。また、産科医と助産師が真の意味で協働し、それぞれの専門性を生かしたより良いケアを実現するためには、「制度の見直しや教育改革が必要」とも感じていました。そうした中、イギリスの国立医療技術評価機構(National Institute for Health and Care Excellence)による「NICEガイドライン」が、自分にとっての一つの指針になるのではと思うようになり、渡英して公衆衛生を学ぶことにしたのです。でも……。正直、英語が得意だったわけではないので、当時は夜勤をしながら語学のスパルタ塾に通うことになりました。
1年間の留学中は、大学院で学ぶかたわら助産師として働く方たちにインタビューしたり、現地の医療機関を見学したりしていましたね。イギリスでは「正常なお産のプロフェッショナル」として助産師が高い信頼を得ており、産科医がまったく介入しないケースも少なくないのですが、そうした日本とは違うやり方、考え方に触れることで、本当に勉強になったと感じています。
臨床経験を武器に医療政策を変えていく

帰国後は、母子保健や産科医療に関する政策提言ができる存在を目指して、特定非営利活動法人 日本医療政策機構(HGPI)に入職しました。HGPIは医療政策に関する調査・研究を行うシンクタンクで、現在私が担当しているのは「女性の健康」「患者・当事者プラットフォーム」「医療者の働き方改革」「医療政策アカデミー」の4つのプロジェクトです。
基本的には、産官学民(産業界、官公庁、教育・研究機関、市民団体)のステークホルダーを結集して政策提言を行っていくのですが、その際、特に意識しているのが一般市民の視点を大切にすること。たとえば、働く女性に関する政策提言なら、一般の働く女性2,000人にアンケートして生の声を集めます。また、大学生への性教育については現役の大学生にヒアリングを行ったり、非感染性疾患の分野ではがんや糖尿病など様々な疾患の患者・当事者リーダーにワーキンググループメンバーとして議論に参加してもらったりすることもあります。そうやって当事者を巻き込みながら、多様な視点から議論を重ね、論点や課題を整理しながら政策提言としてまとめていくわけです。もちろん、政策を変えるのはとても難しいことですが、それでも、自分たちの働きかけがきっかけとなって、少しずつ社会が動いていくのは、とてもインパクトのある活動。このうえない充実感を感じます。
提言はウェブで公開するほか、関連省庁の担当者や議員へ直接コンタクトするケースもあります。特に医療分野出身の方は、私が助産師として働いていたことで親近感を持ってくださり、コミュニケーションが円滑に進むことも少なくありません。逆に、医療現場のことを知らないメンバーで話し合うときは、現場の実態について意見を求められる機会も多く、そんなときは医療職経験者としての強みを感じます。
転職で変わったことといえば、ワークライフバランスにも変化がありました。多忙な毎日であることに変わりはありませんが、病院勤務ではあり得ない土日休みや年末年始の連休がとても新鮮です。2歳の娘がいるので、家族で過ごせる時間が増えたことは素直にうれしいですね。ただ、臨床業務と違って、デスクワークは自宅に持ち帰れてしまうので、その点は要注意。仕事に追われすぎるようなことのないよう、気持ちをしっかりと切り替えなくてはなりません。でも、全体的にみれば、生活にメリハリができて、以前より仕事もプライベートも楽しめるようになった気がします。
有資格者だからこそ思い切ったチャレンジができる!

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大で、2020年の医療現場は大変な状況に見舞われました。現場でがんばっている医療従事者のみなさんには、感謝と尊敬の気持ちしかありません。みなさんがリスクをいとわず奮闘されている中、何もできない自分が歯がゆく、落ち込んだ時期もあったのですが……。日本看護協会にアプローチしてみたところ、看護職に対する危険手当の支給などを求める要望書のお手伝いをさせていたくことができ、ほんの少しだけ役に立つことができました。
また現在は、以前に勤務していた産科クリニックのオンライン両親学級を運営したり、区の保健センターで育児・母乳相談を行ったりと、現場に近い仕事にも月に数回ほど関わっています。そして、そうした活動は「助産師の今村」に戻れる貴重な機会であり、私にとってとても大切な時間になっています。「育休を取った夫が育児に参加してくれない」などのリアルな悩み相談に乗る中で、自分自身の勉強になることがたくさんありますし、現場に身を置き続けることで、数字やデータ以上に“説得力のある言葉”が身につくと思うんです。
今、新たな道を模索している看護職の方にお伝えしたいのは、「興味があることには臆せず挑戦して!」ということです。医療従事者としての資格があるのは大きな強みであり、現場に戻りたいと思えば復帰できるのですから、チャレンジングなことにも取り組みやすいはず。ひと昔前に比べて、医療従事者が活躍できる場も大きく広がっているので、多様な選択肢があることを忘れず、視野を広く持ってみてください。一つだけアドバイスをするとしたら、アクションを起こす際は、まず「楽しく働いている人」を探して、コンタクトをとってみてください。経験上、そうした人のまわりには、同じようにポジティブで魅力的な人が集まっているので、いい刺激がたくさん得られるはずですよ。
取材・文:ナレッジリング(中澤仁美) 撮影:ブライトンフォト(和知 明)