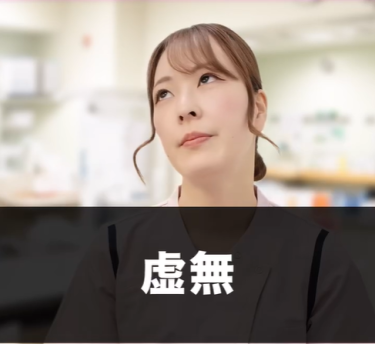日本語には、ひらがな・カタカナにくわえて多くの漢字があります。漢字のなかには、同じ表記でも読み方が異なるものが多々あり、正確に何と読むのか曖昧になっているケースも少なくありません。たとえば、「発疹」という漢字は、ハッシンとホッシンどちらで読むのが正しいのか分からないという方もいるでしょう。
当記事では、発疹の正しい読み方や意味、湿疹との違いにくわえて、紅斑や丘疹といった発疹の種類、引き起こされる原因などを解説します。
「発疹」の読み方はハッシン? ホッシン?
日本語の使い方は難しく、発疹と書いて何と読むのか、曖昧な方もいるかもしれません。ニュース番組でアナウンサーが「ハッシン」と読んでいるときもあれば「ホッシン」と読むときもあります。 そのため「ハッシン」「ホッシン」のどちらが正しい使い方なのか、気になる方もいるでしょう。
伝統的には「ハッシン」と読まれていますが、一般的には「ホッシン」と読むケースも多いため、どちらの読み方でも通用します。
NHKでは、発疹の読み方について以下のように用語の決定をしています。
*用語の決定
発疹 NHK 表記
発疹 ①はっしん②ほっしん
(これまでは ○はっしん ×ほっしん)
医療業界で働くうえで、どちらの読み方でも正しい意味が伝わるため、大きな問題はありません。
発疹の正しい意味は? 湿疹との違い

発疹とは、皮膚そのものに現れる見た目の変化「皮疹(ひしん)」の1種です。数時間または数日のうちに急にできた皮疹を「発疹」と呼びます。発疹は、目で見て分かる皮膚の変化(症状)を指します。したがって、見た目で分かる形・色・大きさ・質感や、発疹の原因は1つではありません。
また、発疹と混同されやすい言葉に「湿疹(しっしん)」があります。湿疹は発疹の1種の皮膚病変であり、イコールではありません。
発疹と湿疹の違い
発疹と湿疹は似た言葉ではありますが、同じ症状ではなく違う状態です。では、発疹と湿疹の違いについて解説します。
| 発疹とは |
|---|
| ウイルス感染、かぶれ、かゆみ、水疱、吹き出物、蕁麻疹などが、急に現れる皮膚の変化のことです。 |
| 湿疹とは |
|---|
| アトピー性皮膚炎といった持続して出ている皮膚の変化のことです。厳密には、病気の名前であり、皮膚表面に起きるさまざまな炎症を意味します。また、皮膚炎と呼ばれる症状とも同じ意味です。 |
急にできた皮膚の変化が発疹、持続して皮膚に炎症が起きている症状が湿疹と考えると、覚えやすいです。
発疹の種類

目で見て分かり手で触れる皮膚の病変を発疹と呼び、状態に応じていくつかの種類に分類されます。大別すると、多様な色調の変化で凸凹のない「斑」、ブツブツして盛り上がっている「丘疹・結節・腫瘤など」、ブツブツして皮膚に体液や膿が溜まる「水疱・膿疱など」です。
さらに詳細に分けられるため、発疹の種類と読み方、特徴を解説します。
| 発疹の種類 | 読み方 | 特徴 |
|---|---|---|
| 紅斑 | コウハン | 皮膚と同じ高さの赤い斑点で、境界がはっきりしています。皮膚の毛細血管が拡張して出る症状です。赤みを消すには圧迫する必要があります。紅斑は、血管の色によって起きる「色素斑」で、色素沈着や色素の欠落による「斑」とは、別タイプです。 |
| 丘疹 | キュウシン | 皮膚表面から隆起したもので、多くの場合は赤みを帯びた状態です。丘疹の大きさは、直径10mm以下で、ブツブツしたできものになります。丘疹の頂点に小さな水疱がある場合は「漿液性丘疹(しょうえきせいきゅうしん)」と呼ばれ、湿疹に固有のもので、発疹とは別物です。 |
| 膨疹 | ボウシン | 虫さされ跡のような見た目で、膨れている赤い斑のことです。皮膚の一部がむくんでおり、盛り上がりは平たいタイプです。蕁麻疹を発症したときに出てくるものになります。赤みやかゆみが出ますが、24時間以内に消えて痕を残しません。 |
| 水疱(水ぶくれ) | スイホウ | 透明な液体が皮膚に溜まっている状態です。膿をもち、黄色く濁ってくると「膿疱(のうほう)」という状態になります。「にきび」や「とびひ」も膿疱に含まれます。 |
| 痂皮 | カヒ | 水疱や膿疱が破れて、中に溜まっていた液体が厚く固まった状態です。一般的に「かさぶた」と呼ばれています。血液が混ざったものは「血痂(けっか)」、膿が混ざって黄色いかさぶたができたものは「膿痂(のうか)」です。 |
| 鱗屑/落屑 | リンセツ/ラクセツ | 鱗屑とは、剥がれ落ちた角質が、皮膚表面に付着している状態です。頭皮のフケ、皮膚をひっかいたときの白い粉などが鱗屑と呼ばれます。 また、鱗屑が皮膚表面から剝がれ落ちることを落屑といいます。 |
| きれつ(ひび、あかぎれ) | – | 皮膚にできる線のような細い裂け目のことです。乾燥や炎症により発症し、手の指や足の裏などができやすい部位になります。多くの場合は、角質から表皮に発症しますが、真皮にまで及ぶものもあります。 |
| びらん(ただれ) | – | 表皮の一部が剥がれる、水疱や膿疱が破れるときに、鮮紅色のただれた皮膚がむき出しになっている状態です。表皮だけが剥がれた状態のため、治った後は痕が残りません。 |
| 潰瘍 | カイヨウ | 真皮や皮下組織にまで及ぶ皮膚の欠損のことです。治ったのちに痕が残ります。 |
| 結節/腫瘤(こぶ) | ケッセツ/シュリュウ | 皮膚腫瘤の1種であり、皮膚が盛り上がり、かたまりになった状態が結節です。結節よりも大きいかたまりは、腫瘤と呼ばれます。大きさの目安は、結節が10~30mmで、腫瘤は30mm以上です。 |
発疹にはさまざまな種類がありますが、皮膚病の観点からして1つの病気の発疹は1種類とは限りません。同時に2種以上の発疹が出る場合もあります。たとえば、水疱から膿疱になる、水疱からびらんになり痂皮ができるなどの状態です。1つの発疹がほかの発疹に変わっていき、同時に数種の症状が出ることもよく見られます。
皮膚に赤みや腫れが見られたとき、憶測で「にきび」「吹き出物」などと自己判断する方もいます。しかし、原因や症状の詳細、いつから発症したのかなどを考えることにより、正しい対応ができるでしょう。
■関連記事
「蝶形紅斑」って読める?別名バタフライ・ラッシュ、その意味は?【医療漢字クイズ】
発疹ができる原因とは?

発疹ができる原因と症状について、解説します(湿疹やそのほかの皮膚炎についても触れています)。
・ウイルス感染
はしか、水ぼうそう、風疹、突発性発疹、手足口病などのウイルスに感染して発症する発疹です。原因ウイルスへの感染症治療を行い、発疹を改善させます。
・細菌感染
溶連菌感染症といった細菌に感染して発症する発疹です。皮膚に細菌が侵入すると、好中球がマクロファージ菌を食べて、リンパ球が抗体を出して攻撃をはじめます。その際に、生理活性物質が発生するため、皮膚炎が起きます。
・アレルギー物質
動物、洗剤、金属、花粉、化粧品、薬物、ハウスダスト、植物、化学物質など刺激を与える原因物質、アレルギー源となる物質に接触すると発症する発疹です。アレルギー反応により、接触性皮膚炎、かぶれという状態になることが多いです。たとえば、金属アレルギーを知らずにアクセサリーを付けた部位に発疹が起きることもあり「金属かぶれ」とも呼ばれます。
・多量の汗
多量の汗によって、あせもが発症します。
・アトピー性皮膚炎
アトピー性皮膚炎になると、耳、顔、首、腕、足などに湿疹が出ます。皮膚全体がカサカサしているため、痛そうに見えるケースも少なくありません。
・脂漏性湿疹
皮脂の分泌異常、ホルモンバランスの乱れなどが原因で発症する湿疹です。鼻まわりの皮膚が赤く炎症を起こします。
湿疹は皮膚に炎症を起こす病気の総称で、かぶれは「接触皮膚炎」と呼ばれます。湿疹のなかでも、外部からの刺激が原因だと明確になっている場合には「かぶれ・接触性皮膚炎」と判断できます。
発疹や湿疹ができる原因は多様です。また、発疹の種類も多いため、自己判断ではなく、きちんと原因と症状を照らし合わせて合致させることが、正しい治療を目指すポイントです。
まとめ
発疹は、これまで伝統的には「ハッシン」、一般的には「ホッシン」と呼ばれていました。近年では、ホッシンの読み方が広く浸透していることを受けて、NHKはどちらの読み方でも問題ないとしています。また、発疹の種類は複数あり、その違いを理解したうえで正しい治療を受けることが大切です。
現在、医療分野の勉強をしており、将来的に看護師を目指したいと考えている方は、ぜひマイナビ看護師にご相談ください。マイナビ看護師では、医療業界に精通したキャリアアドバイザーが条件に合った求人を提案いたします。まずは、お気軽に無料転職サポートをご利用ください。
※当記事は2024年2月時点の情報をもとに作成しています
-

今話題のトラベルナース!短期間かつ高給与の求人が揃ってます!
-

転職先で給与アップしたい方へ★
年収500万円以上の高収入求人や応募のポイントをご紹介! -

人気の転職時期である4月に転職するメリットはたくさん!
-

働きながら綺麗になれる♪常に人気の美容クリニック求人をピックアップ!
-

企業でも看護師資格を活かして働けます!ワークライフバランス◎
-

シフト勤務の環境を変えたい方向けに、土日祝休みの求人をご紹介!
-

看護師さんの約半分は夜勤なしで勤務中!無理なく働ける夜勤なし(日勤のみ)求人をご紹介!