ケルニッヒ徴候(Kernig徴候)は、髄膜炎や脳炎、くも膜下出血といった中枢神経系の疾患において重要な所見とされ、早期発見と適切な介入が求められます。患者さんの状態を正確に把握し、効果的なケアと迅速な医療連携を実現するには、実践的な知識の習得が必要です。
当記事では、ケルニッヒ徴候に関する基礎知識から陽性となった場合の対応方法まで、詳しく説明します。現場で役立つ情報を分かりやすく解説していますので、ケルニッヒ徴候について理解を深めたい方や情報収集している方はご一読ください。
本多 洋介(新東京病院所属)
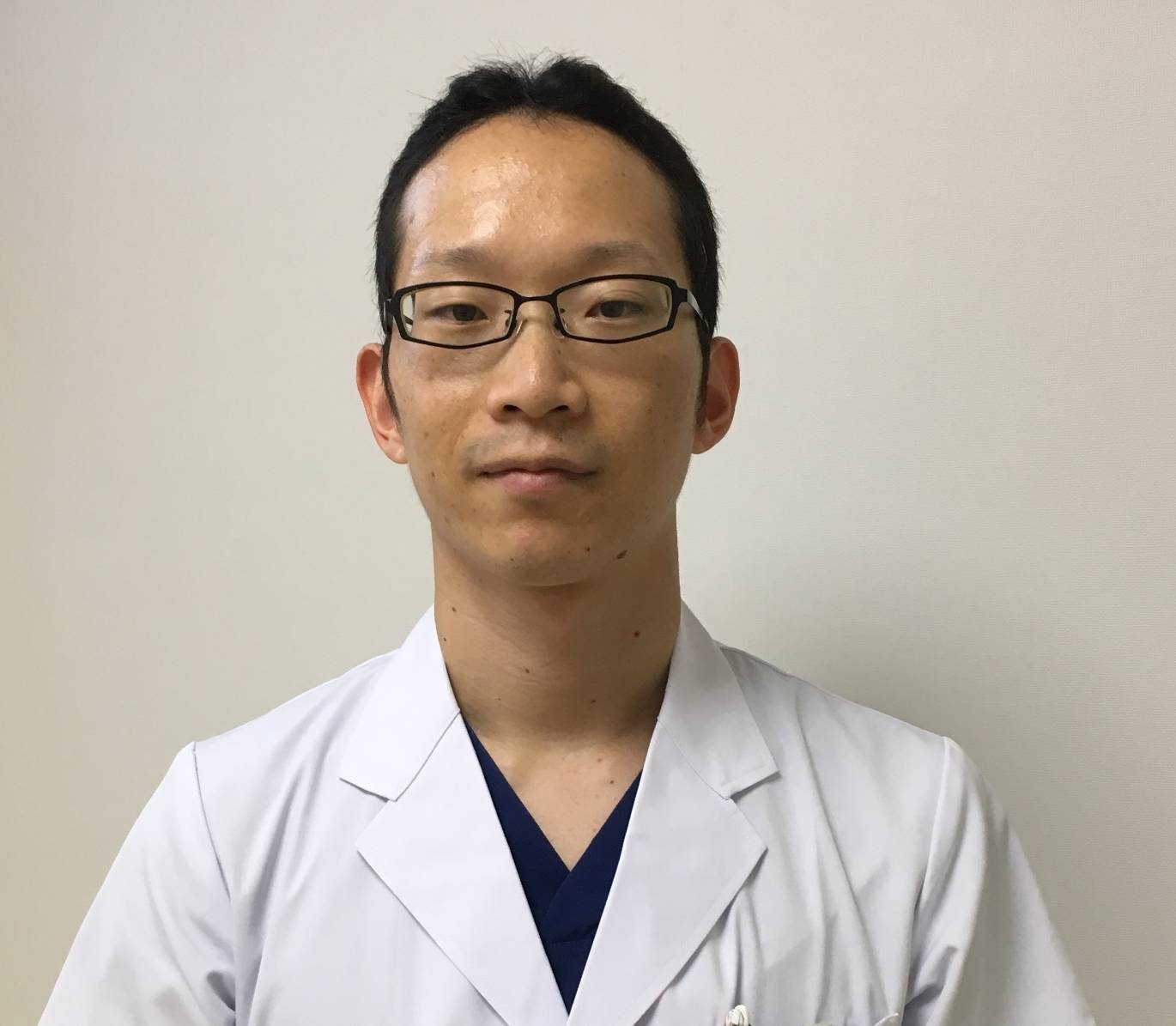 |
岡山大学医学部卒業 / 現在は新東京病院勤務 / 専門は整形外科、脊椎外科。 |
ケルニッヒ徴候とは?
ケルニッヒ徴候(ケルニッヒちょうこう)とは、髄膜刺激症状の1つであり、髄膜炎など中枢神経系の炎症の疑いを示す重要な所見です。患者さんを仰向けに寝かせて一側股関節を直角に曲げ、膝を押さえながら下肢を被動的に伸展すると抵抗や疼痛を感じ、十分な伸展が得られない現象を指します。
髄膜刺激症状とは、感染や出血などにより髄膜が刺激され、頭痛や項部硬直、嘔吐などが現れる状態です。脊髄神経根の炎症・浮腫によって、疼痛や筋攣縮が生じる場合もあります。
ケルニッヒ徴候とラセーグ徴候の違い
ラセーグ徴候とは、仰向けに寝た患者さんの下肢を伸展しながら持ち上げる際、大腿後面に坐骨神経由来の疼痛が生じ、足の挙上が困難になる現象です。この際、ケルニッヒ兆候とは異なり膝を曲げずに行います。椎間板ヘルニアなど坐骨神経障害の鑑別に用いられます。
一方、ケルニッヒ徴候は、仰向けで下肢を曲げ伸ばしする際に抵抗や疼痛により伸展制限を認める所見で、髄膜炎など中枢神経系の炎症を示唆します。つまり、ケルニッヒ徴候とラセーグ徴候では、検査手法や示す疾患が異なる点が大きな違いといえるでしょう。
ケルニッヒ徴候の評価方法

ケルニッヒ徴候の評価方法は、まず患者さんを仰向けに寝かせ、股関節と膝関節を各90度に屈曲させた状態から膝関節をゆっくりと伸展し、膝が135度以上に完全に伸びるかどうかを確認します。
135度以上の膝の伸展が困難で、腰部や下肢に痛みが現れる場合は、ケルニッヒ徴候が陽性と判断され、髄膜炎などの髄膜刺激症状が疑われます。なお、評価の際は患者さんに事前説明したうえで協力を得ることが大切です。
(出典:日本救急看護学会 セミナー委員会「救急初療看護に活かすフィジカルアセスメントミニガイド」)
(出典:関⻄医科⼤学 脳神経内科「神経診察のポイント」)
ケルニッヒ徴候はなぜ起こる?

ケルニッヒ徴候は、髄膜炎や脳炎、くも膜下出血など、各種中枢神経系疾患による髄膜刺激が関与して発現するケースが多い傾向にあります。ここからは、各疾患の概要と原因について詳しく解説します。
髄膜炎
髄膜炎とは、脳や脊髄を包む髄膜に炎症が起こる疾患です。細菌、ウイルス、結核菌や真菌などの感染性病原体が原因になることが多く、髄膜炎は「ウイルス性髄膜炎」と「細菌性髄膜炎」に大別されます。
どちらの場合でも、発熱や頭痛、首の硬直、嘔吐などが主な症状です。特に細菌性髄膜炎は重篤になることが多く、早期の診断と治療が求められます。一方、ウイルス性髄膜炎は比較的症状が軽く経過する傾向にありますが、患者さんの免疫状態により症状は異なります。
脳炎
脳炎とは、脳内に白血球が侵入して炎症を引き起こす疾患です。「感染性脳炎」と「自己免疫性脳炎」に大別されます。感染性脳炎では、原因が判明した急性ウイルス性脳炎の約60%が単純ヘルペスウイルスによって引き起こされているといわれています。水痘帯状疱疹ウイルス、サイトメガロウイルス、ウエストナイルウイルスなども原因になるほか、細菌や原虫による症例もあります。一方、自己免疫性脳炎では、ウイルス感染やワクチン接種、がんに伴う免疫反応により、免疫系が誤って脳組織を攻撃することが主な要因です。
脳炎の主な症状は、発熱や頭痛、意識障害、けいれん、錯乱などです。脳炎が進行すると運動・言語障害が発症する可能性があるため、重症化防止には早期診断と迅速な治療が求められます。
くも膜下出血
くも膜下出血とは、脳を覆うくも膜下腔に急激に出血が起こる重篤な疾患です。通常、くも膜下出血は頭部の外傷により引き起こされます。しかし、原因が非外傷性の自然出血の場合、くも膜下出血は脳卒中とみなされます。非外傷性のくも膜下出血の主な原因は脳動脈瘤の破裂で、特に40~65歳の女性に多い傾向です。
脳動脈瘤の破裂時は雷鳴頭痛や顔面・眼の激しい痛み、短時間の意識消失が出現し、出血が脳脊髄液の流れを阻害して水頭症などの合併症を引き起こすこともあります。脳動脈瘤ができるのは遺伝や喫煙、高血圧や動脈硬化などの疾患による場合もありますが、ほとんどは原因不明です。
ケルニッヒ徴候が陽性だった場合は?

ケルニッヒ徴候が陽性の場合、ただちに医師へ報告し、確定診断のための脳脊髄液検査(腰椎穿刺)の準備を進めます。髄膜炎やほかの中枢神経系疾患が疑われるため、患者さんの状態やバイタルサインを注意深く観察し、悪心や嘔吐などの症状が強い際には医師に薬剤の検討なども打診しましょう。
腰椎穿刺時は、円滑に検査できるよう患者さんを適切な体位に誘導し、禁忌の有無や同意確認などを徹底します。意識レベルの低下や麻痺があるために、患者さんが自分で体位を保持できない場合は患者さんの前面に立ち、首の後ろと膝窩部を抱えて、腰を曲げるような体位をとり、腰椎の棘突起が広がるようにして支えます。腰椎穿刺・髄液採取などは医師が行うため、清潔区域を不潔にしないよう注意しながら介助しましょう。検査により提出量は異なるため、事前に医師に確認のうえ、必要なスピッツの本数を準備することも大切です。
検査後は頭痛や頭重感などの合併症が生じやすいため、頭位を低くして1~2時間は安静を保つようにしましょう。頭痛や悪心、嘔吐などの症状がある場合、穿刺部位から髄液が漏れ出ている場合、38.5℃以上の発熱がある場合などは、医師に速やかに報告します。
髄膜刺激症状や髄膜炎の看護ポイント

髄膜刺激症状や髄膜炎の疑いがある患者さんには、バイタルサインや症状の変化をこまめに観察し、けいれん発作に迅速に対応できるよう準備するのが一般的です。ここからは、具体的な看護の進め方やポイントを解説します。
髄膜刺激症状の出現の有無やバイタルサインなどをよく観察する
髄膜刺激症状の有無やバイタルサインの変化は、髄膜炎や脳炎の早期発見に極めて重要です。患者さんを仰臥位にして項部硬直を確認し、ケルニッヒ徴候では下肢の伸展抵抗、ブルジンスキー徴候では頭部前屈時の自動的な股・膝屈曲、ジョルトアクセンチュエイション(首を左右に振る)により頭痛の悪化をチェックします。
髄膜刺激症状の出現の有無や程度のほか、患者さんからの訴えやバイタルサインの変化などをこまめに確認し、異常が認められた場合は速やかに医師へ報告と必要な介入を行うようにしましょう。
けいれん発作に備えておく
髄膜刺激症状や髄膜炎が疑われる患者さんでは、意識障害やけいれん発作が急激に起こる可能性があります。常に呼吸状態をモニターし、必要な酸素投与や吸引器、ジアゼパムなどの抗けいれん薬の準備を整え、発作発現時に迅速かつ冷静な対応ができるよう備えるとよいでしょう。
けいれんの発見者となったときは、まず緊急コールや大声で応援を要請し、バイタルサインを測定しながらけいれんの出現部位や前駆症状の有無・様式、持続時間などを観察します。意識状態が悪化した際は、気道確保や酸素投与などの対応が必要です。
まとめ
ケルニッヒ徴候とは、仰向けで下肢を伸展する際に膝の完全な伸展動作が困難となり、抵抗や痛みを感じる現象です。髄膜炎など中枢神経系疾患の疑いを示す臨床的な所見となるため、患者さんの状態変化を見逃さず、疾患の早期発見と適切な介入に努めることが求められます。ケルニッヒに関する知識を活かし、患者さんの安全確保と早期治療に結び付けることで、安心できる看護ケアの実践に役立てていただければ幸いです。
マイナビ看護師では、看護師の皆さんのキャリアやスキルアップをサポートしております。看護職専門のキャリアアドバイザーが転職活動を支援いたしますので、お気軽にご相談ください。
※当記事は2025年2月時点の情報をもとに作成しています
-

今話題のトラベルナース!短期間かつ高給与の求人が揃ってます!
-

転職先で給与アップしたい方へ★
年収500万円以上の高収入求人や応募のポイントをご紹介! -

人気の転職時期である4月に転職するメリットはたくさん!
-

働きながら綺麗になれる♪常に人気の美容クリニック求人をピックアップ!
-

企業でも看護師資格を活かして働けます!ワークライフバランス◎
-

シフト勤務の環境を変えたい方向けに、土日祝休みの求人をご紹介!
-

看護師さんの約半分は夜勤なしで勤務中!無理なく働ける夜勤なし(日勤のみ)求人をご紹介!




