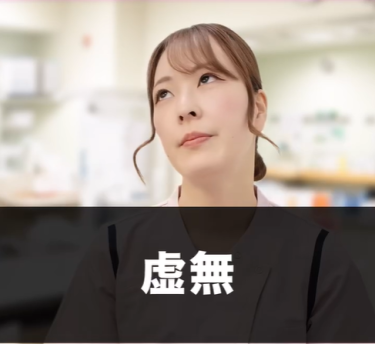『エキスパートナース』2015年12月号<術後のつらさを改善する【10項目】 ナースができる! ERAS®(イーラス)術後回復能力 強化プロトコル>より抜粋。第7回は《各論》術後回復を助けるための”エッセンス”10項目の「項目4【術中、術後】輸液量は大丈夫? 過剰でもダメ、不足でもダメ!」を紹介いたします。

清水 拓也 (東北大学病院 移植・再建・内視鏡外科(血管外科)助教/気仙沼市立病院血管外科)
輸液は過剰でも不足でも臓器障害に。だから適正な管理が重要
ERAS®の推奨項目には過剰な輸液やNa負荷を避けることが推奨されています。
従来の術中輸液管理では、血圧、脈拍、尿量などをモニタリングしながら、不感蒸泄や出血量、サードスペースを考慮して輸液を行うために、過剰輸液となる傾向にありました。過剰輸液により全身臓器が浮腫状になれば、臓器障害が引き起こされると考えられます。特に消化管では、腸管浮腫のために吸収障害やイレウスなどが生じ、術後の腸管機能回復が遅延する可能性があります(引用文献1)。
一方、過剰輸液を避けるため過度に輸液を制限すれば、脱水となり、腎不全や、心筋虚血、脳血管障害などが引き起こされる可能性があります。
そのため、安全な周術期管理を行うためには適正な水分バランスを保つことが重要ですが(図1/引用文献2)、適正な輸液のための明確な基準はないのが現状です。
■関連記事
術中はGDT、術後は補液の減量・中止をめざす
予後改善という目標を達成するために適正な輸液を行う、目標指向型の輸液療法(goal-directed fluid therapy、GDT)という概念が提唱されています。これは術中の1回拍出量(stroke volume、SV)や1回拍出量の変動(stroke volume variation、SVV)などの循環動態の鋭敏な動的パラメータを指標として、個々の患者に必要最低限の輸液を行い、全身への酸素供給量を維持する(輸液の最適化)ものです。晶質液の過剰投与を避けるため、膠質液(アルブミンやヒドロキシエチルデンプン〈HES〉製剤)を投与することもあります。
GDTによる輸液の最適化の結果、術後感染症や心血管イベントの発症が抑制され、ICU滞在期間も短縮されたことがメタアナリシスで報告されています(引用文献3)。
術後は早期経口摂取がERAS®では推奨されています。経口摂取が可能になれば、補液を減量・中止すべきであり、漫然と継続するのは好ましくありません。過剰輸液による臓器障害を防止すると同時に、不必要な輸液ラインを外すことにより、術後早期離床にもつながります。
■関連記事
術後1週間は体重測定を行う
図1 術後輸液量による身体への影響と対応

術後に適正な水分管理を行うためには、in-outバランスを計算することはもちろん、体重の推移を把握することが大切です。術後1週間は体重測定を行い、水分バランスを評価しましょう。 術前体重よりも体重が多く経口摂取が見込まれる状況では、補液を中止して経過観察してもよいでしょう(図1-①)。
一方で、経口摂取が不十分な状態が続き、術前体重よりも減少していれば脱水のリスクが高く、補液を行う必要性が高いと判断されます。また、補液の判断の精度を高めるために、ベッドサイドでの問診・身体観察も積極的に行いましょう。バイタルサインに加えて、口渇感、口腔内粘膜の乾燥など、脱水の可能性を示唆する身体所見から補液の必要性の判断を行うことが重要です(図1-②)。
脱水や過剰輸液による合併症予防のために、体重や身体所見をもとに、総合的に判断することが重要です。そのほか、ICUなど術直後は血液ガス分析(pH、BE、乳酸値)なども参考にしましょう。
■関連記事
1. Prowle JR,Echeverri JE,Ligabo EV,et al.:Fluid balance and acute kidney injury.Nat Rev Nephrol 2010;6(2):107-115.
2.Bellamy MC:Wet,dry or something else?.Br J Anaesth 2006;97(6):755-757.
3.Benes J,Giglio M,Brienza N,et al.:The effects of goal-directed fluid therapy based on dynamic parameters on post-surgical outcome:a meta-analysis of randomized controlled trials.Crit Care 2014;18(5):584.

東北大学病院 移植・再建・内視鏡外科(血管外科) 助教/気仙沼市立病院 血管外科
本記事は株式会社照林社の提供により掲載しています。/著作権所有(C)2015照林社
[出典]エキスパートナース2015年12月号 P.68~「術後のつらさを改善する【10項目】 ナースができる! ERAS ®(イーラス)術後回復能力 強化プロトコル」