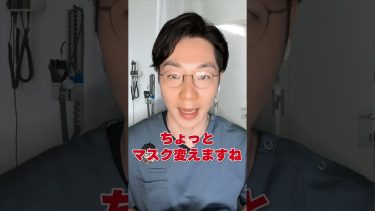骨髄穿刺は、血液をつくり出す骨髄の状態を直接観察するために行われる検査です。採取した骨髄液や細胞を調べることで、白血病や悪性リンパ腫、多発性骨髄腫などの血液がんや、重度の貧血などの原因を見極めるための情報が得られます。
侵襲的な手技であるがゆえに、患者さんは不安や痛みを訴えることが少なくありません。検査を安全かつ確実に進められるように、患者さんが安心して検査を受けられるようにするのも、骨髄穿刺における看護師の重要な業務です。
この記事では、骨髄穿刺の概要や介助の方法、注意点について解説します。
中松繁 治(新東京病院所属)
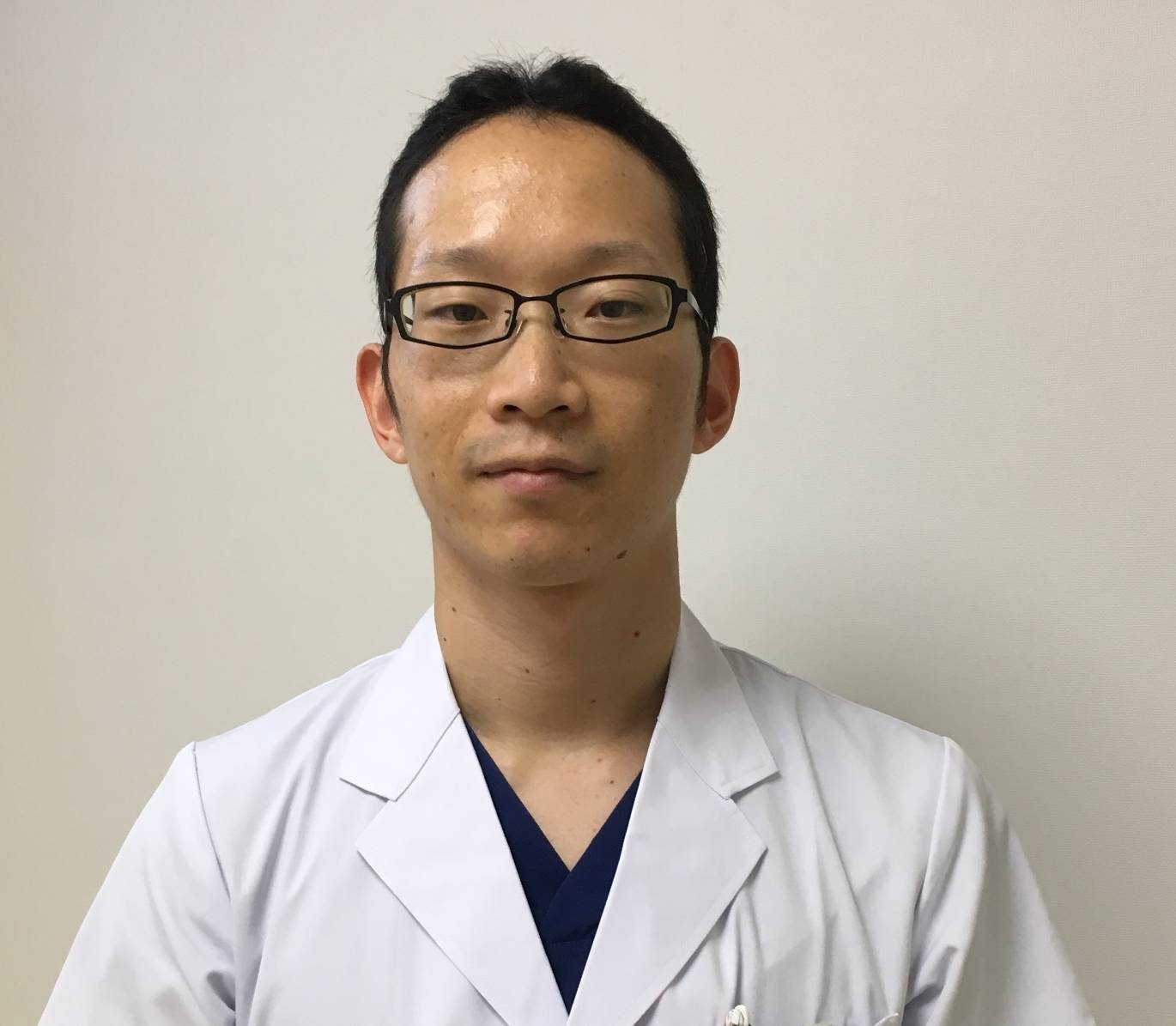 |
岡山大学医学部卒業 / 現在は新東京病院勤務 / 専門は整形外科、脊椎外科 |
骨髄穿刺とは?
骨髄穿刺とは、骨髄に針を刺して骨髄液と細胞を採取する検査のことです。骨髄穿刺は骨髄検査の1つであり、骨髄サンプルを採取・観察することを目的として実施されます。
赤血球・白血球・血小板などは、骨の中にある骨髄組織でつくられます。血球の異常が見られる場合は、骨髄穿刺によって骨髄液・細胞を調べることで原因の特定が可能です。
骨髄穿刺を実施すると、骨髄の中にある細胞の種類やそれぞれの細胞の大きさ・数・特徴に関する情報を得られ、骨髄細胞の形状・染色体の異常の有無を判断できます。
骨髄穿刺では、腸骨に注射器を刺して骨髄液を吸引するのが一般的です。ただし、腸骨穿刺が難しい場合は胸骨から穿刺するケースもあります。
2種類の骨髄検査
骨髄組織を採取する骨髄検査は、骨髄穿刺と骨髄生検の2種類です。
骨髄穿刺と骨髄生検は、どちらも腸骨または胸骨から骨髄組織片を採取し、検体を顕微鏡で観察する検査という点では共通しています。しかし、骨髄穿刺では注射器を使用し、骨髄液と細胞を吸引するのに対し、骨髄生検では特殊な太い針を使用し、骨髄組織の一部を採取する点が違いです。
検査で分かること
骨髄穿刺・骨髄生検は、血液を造る機能の状態、血液疾患の原因、腫瘍細胞の有無などを調べるために行われる検査です。白血病や悪性リンパ腫、多発性骨髄腫などの血液がんや、再生不良性貧血などの血液疾患の診断に役立ち、ひいては治療方針の決定、治療効果の判定にも必要です。
また、骨髄検査は白血球数の増減や貧血、末梢血への異常細胞出現などが見られる場合にも実施されます。
そのほかには、以下のような目的で検査を実施します。
- 骨髄造血能の評価
- 造血器腫瘍の診断・病型分類
- 悪性腫瘍の骨髄転移の有無
- 先天性代謝異常の診断
骨髄穿刺の介助の方法

骨髄穿刺は医師が実施するため、看護師はそれを介助するのが基本です。看護師が骨髄穿刺をサポートする際の手順は、以下の通りです。
| 1 | 必要物品を準備する |
|---|---|
| まずは骨髄穿刺に必要な物品を用意しましょう。必要物品には骨髄穿刺の専用針や専用スピッツ、注射器、注射針のほか、消毒液や穴あき滅菌ドレープ、滅菌手袋、滅菌ガーゼ、滅菌ガウン、局所麻酔薬、絆創膏などが挙げられます。 | |
| 2 | バイタルを測定して体位を整える |
| 患者さんに骨髄穿刺の必要性と検査の流れを説明後、排尿を促してバイタルサインを測定します。また、骨髄穿刺は患者さんが医師に背を向けた状態で上になる脚の膝を曲げた体勢で行うため、必要な体位を整えてもらいましょう。 | |
| 3 | 消毒・麻酔の介助をする |
| 皮膚を消毒したら、患者さんにドレープをかけます。次に、穿刺部位の皮膚に局所麻酔薬で麻酔を実施し、そのまま針先を進めて骨髄にも麻酔します。看護師は必要に応じて消毒・麻酔の介助を行いましょう。 | |
| 4 | 穿刺中の患者さんの様子を確認する |
| 麻酔が十分に効いているのを確認したら医師が穿刺を実施するため、看護師は患者さんの状態を確認しながら声かけを行います。検査中は患者さんが医師に背中を向けた状態であり、医師は手技に集中していることから、患者さんの状態は看護師が適切に把握する必要があります。痛みの度合いや顔色、呼吸状態、脈拍などを注意深くチェックしましょう。また、痛みを感じる場面で患者さんに声かけをするなどのサポートも役立ちます。 | |
| 5 | 圧迫止血の介助をする |
| 抜去後は医師が圧迫止血の処置をするため、医師に滅菌ガーゼを手渡して止血を介助しましょう。また、患者さんに穿刺が終了した旨を伝え、出血が完全に止まるまで動かないよう指導します。止血が完了したら、患部を滅菌ガーゼで固定しましょう。 | |
| 6 | 検査後のバイタルサインを測定する |
| 最後にもう一度バイタルサインを測定し、症状がないことを確認したら検査終了です。検査後30分程度は仰臥位で安静を保ち、穿刺部位からの出血に注意して観察を行います。胸骨穿刺の場合は、必要に応じて砂嚢を使用してください。また、患者さんには当日の激しい運動や入浴を控えるのがよい旨を指導しましょう。 | |
骨髄穿刺に痛みはある?
骨髄穿刺では、局所麻酔の針を刺す際にチクッとした痛みを感じるほか、骨の表面も針を刺すことによって痛む場合があります。
局所麻酔後の穿刺時は、麻酔が効いているため痛みはありません。ただし、穿刺針で骨に穴をあける際に骨を削られているような感覚を覚える方もいます。
骨髄液を吸引する際には、痛みや違和感を訴えるケースもあります。違和感の種類は「なんとなく気持ちが悪い」「身体を吸い上げられる感覚」などと表現され、患者さんによってさまざまです。
骨髄穿刺を行うときの注意点

骨髄穿刺を行うときは、患者さんの様子をしっかりと観察するのはもちろん、患者さんに寄り添った適切な声かけで精神的サポートを提供することも重要です。
ここでは、骨髄穿刺を実施する際の注意点について詳しく解説します。
事前の情報提供をしっかり行う
骨髄穿刺を実施する際は、患者さんに検査の目的を明確に伝え、できる限り不安が少ない状態で検査を受けてもらうのが理想です。
骨髄検査は病気・不調に関する重要な情報を得られるというメリットがある一方で、侵襲性が高くリスクを伴う側面もあります。安全に検査を終えられることがほとんどですが、稀に局所麻酔によるショックが起こるほか、胸骨穿刺では気胸・大動脈損傷などの合併症が引き起こされるケースもあります。
検査で何が分かるのか・どのようなリスクがあるのかを十分に説明しておくことで、少しでも患者さんの不安を減らせるでしょう。
また、骨髄検査は外来通院にて実施する場合もあります。帰宅後にケアを受けられない状況を患者さんが不安に感じることもあるため、いつまで・どのようなことを避けるべきかを具体的に伝え、患者さんの不安を取り除きましょう。
患者さんの不安に寄り添った声かけをする
骨髄検査を受ける際、患者さんは悪性疾患の可能性もあることを説明されたうえで検査に臨んでいます。そのため、精神的なショックから検査前の説明が頭に入らない方も少なくないでしょう。
看護師には、患者さんの不安な気持ちに寄り添いながら検査に関する補足説明をする・精神面を支えるケアをするなどのサポートが求められます。
また、検査の実施中は患者さんの様子をよく確認し、適宜声かけを行うのが重要です。痛みの有無や強さを把握するだけでなく、顔色や呼吸状態などもチェックしながら声をかけるのがポイントです。
検査の結果、悪性疾患が認められた場合には、患者さんに病態や今後の治療内容について説明することになります。患者さんの反応を確認し、患者さん自身が納得して治療についての意思決定ができるようにサポートしましょう。
まとめ
骨髄穿刺において、看護師は必要物品の準備や麻酔の介助、検査前後のバイタル測定などさまざまな介助を行います。なかでも、検査中看護師にしかできないのが、検査中の患者さんの状態を見ながら、負担や不安に気付いて声かけやケアを行うことです。
血液がんなどの悪性疾患についても検査する関係上、骨髄穿刺の際には強いショックやストレスを感じる患者さんも少なくありません。患者さんの様子をアセスメントしながら、相手の心理的負担を軽減するのが大切です。
マイナビ看護師では、スキルアップやキャリアアップを目指す看護師の方に向けて、看護業界に精通したキャリアアドバイザーが希望に合った職場を紹介します。ぜひお気軽にご相談ください。
※当記事は2025年1月時点の情報をもとに作成しています
-

今話題のトラベルナース!短期間かつ高給与の求人が揃ってます!
-

転職先で給与アップしたい方へ★
年収500万円以上の高収入求人や応募のポイントをご紹介! -

人気の転職時期である4月に転職するメリットはたくさん!
-

働きながら綺麗になれる♪常に人気の美容クリニック求人をピックアップ!
-

企業でも看護師資格を活かして働けます!ワークライフバランス◎
-

シフト勤務の環境を変えたい方向けに、土日祝休みの求人をご紹介!
-

看護師さんの約半分は夜勤なしで勤務中!無理なく働ける夜勤なし(日勤のみ)求人をご紹介!