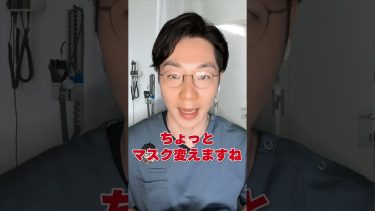頭蓋内圧亢進とは、頭蓋骨内部の圧力が異常に高くなる状態を指し、脳腫瘍や頭部外傷などが原因で生じることがあります。頭蓋内圧亢進は頭痛や嘔吐、視力低下などのさまざまな症状を引き起こし、放置すると脳ヘルニアをきたし生命にかかわる危険性も伴う症状です。
当記事では、頭蓋内圧亢進の基本的な概要、急性期と慢性期の症状の違い、主な原因や発症のメカニズム、さらに診断と治療の方法について詳しく解説します。患者さんの早期回復をサポートしたい方や、急変時の対応力を高めたい看護師の方は、ぜひ参考にしてください。
中松繁 治(新東京病院所属)
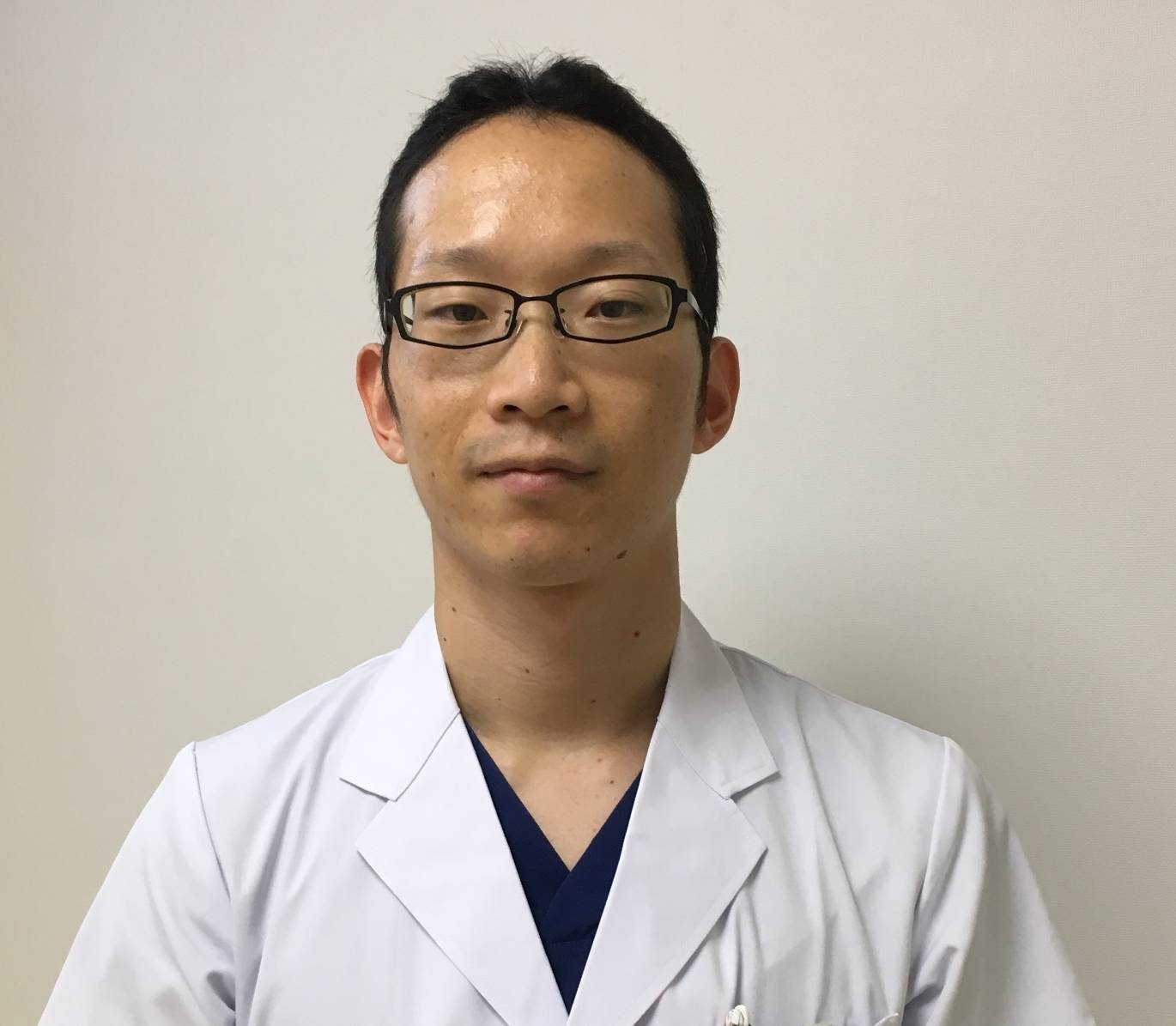 |
岡山大学医学部卒業 / 現在は新東京病院勤務 / 専門は整形外科、脊椎外科 |
頭蓋内圧亢進症状とは
頭蓋内圧亢進(とうがいないあつこうしん)とは脳腫瘍の代表的な症状の1つで、頭蓋内圧が通常以上に高くなることです。頭蓋内圧とは、頭蓋骨の内側に生じる圧力を意味します。
頭蓋内圧は5~15mmHgに維持され、大きく変動しないことが通常です。頭蓋内容は通常、脳実質85%・脳脊髄液10%・血液5%の構成を維持しています。頭蓋内圧亢進症状とは、頭蓋内圧15mmHg以上の亢進状態が継続している際に起こる症状の総称です。
(出典:J-STAGE「各科手術での使用:脳神経外科・脊髄外科手術─頭蓋内圧,神経保護・モニタリング─」)
頭蓋内圧亢進患者さんの看護ケアでは、クッシング現象を意識したバイタルサインの計測に加えてアセスメントを実施し、十分な情報収集に努める必要があります。あわせて、呼吸管理や体位の調整により、頭蓋内圧の亢進を助長しうる因子の除去を図りましょう。
頭蓋内圧亢進の治療法は、浸透圧利尿薬を使用した薬物療法が基本です。頭蓋内圧亢進の原因や薬物療法の結果によっては、外科的治療や外科的治療が選択される可能性もあります。
頭蓋内圧亢進の主な症状

頭蓋内圧亢進の三徴候は、頭痛・嘔吐・うっ血乳頭です。ただし、急性期と慢性期では代表的な症状が異なることから、明確に区別して理解しましょう。以下では、頭蓋内圧亢進の急性期と慢性期における代表的な症状を解説します。
(出典:大学病院医療情報ネットワークセンター「頭蓋内圧亢進」)
急性期の症状
急性頭蓋内圧亢進の症状は、突発的に起こって急速に進行することが特徴です。急性症状としては主に、頭痛・嘔吐・クッシング現象・異常呼吸・瞳孔異常などが確認されます。
クッシング現象とは、急激な頭蓋内圧の亢進によって起こる血圧の上昇と徐脈です。クッシング現象による頭痛は通常、後頭部から前頭部方向へ広がり、体動・咳やくしゃみなどにより悪化します。
急性期・慢性期いずれの症状も放置すると脳ヘルニアに移行するリスクもあり、早急な対処が必要です。脳ヘルニアとは、頭蓋内圧の上昇によって脳が下方や側方へ押し出される症状を指します。押し出された脳が損傷すると不整脈・呼吸困難・麻痺などが起こり、生命にかかわるリスクもあることから、早急な対処が必要です。
慢性期の症状
頭痛・嘔吐・うっ血乳頭の三徴候は、慢性頭蓋内圧亢進に顕著な症状です。慢性頭蓋内圧亢進による頭痛は通常、やや穏やかな痛みが長時間にわたって継続します。慢性頭蓋内圧亢進による嘔吐は「放射性嘔吐」と呼ばれ、食事と無関係に生じることが特徴です。
慢性頭蓋内圧亢進で視神経が圧迫されている場合には、一時的な視野障害も生じる可能性があります。うっ血乳頭が原因の視力低下も、慢性頭蓋内圧亢進で見られる症状の1つです。
頭蓋内圧亢進で血圧が上昇するのはなぜ? 症状の原因も

頭蓋内圧亢進の原因は多岐にわたるものの、脳腫瘍、髄膜炎、水頭症といった緊急性の高い疾患の影響も疑われます。主要な原因で頭蓋内圧亢進が起こり、血圧が上昇するメカニズムは、以下の通りです。
頭蓋内圧亢進のメカニズム
頭蓋骨の内側には脳実質・脳脊髄液・血液があり、容積の和は、一定に維持されています。いずれかが増加した場合、代償機能によってほかの要素が減少するためです。しかし、代償機能には限界があります。頭蓋内圧亢進は、脳腫瘍などの影響で代償機能の限界を超える容積変化が生じ、頭蓋内圧が上昇した状態です。
頭蓋内圧亢進が起こると交感神経が働き、血圧を上昇させます。血圧を上昇させないと脳血流が減少し、脳虚血を起こす危険性があるためです。血圧が上昇すると心拍数を減少させる反応が起こり、徐脈になります。
原発性の原因
原発性の場合には、脳腫瘍の増大や水頭症による髄液の貯留によって一定以上の容積変化が生じ、頭蓋内圧が上昇します。脳腫瘍の場合は圧迫によって損傷を受けた部分に生じる脳浮腫も、頭蓋内圧の上昇を助長する要因です。
(出典:日本臨床外科医学会雑誌「脳圧亢進症の外科」)
稀な病態であるものの、なぜ症状が生じたかを特定できない頭蓋内圧の亢進も存在します。明確な原因を特定できない病態は「特発性頭蓋内圧亢進症」と呼ばれ、妊娠できる年齢の女性に比較的多く見られる点が特徴です。
続発性の原因
頭蓋内圧亢進は、頭部外傷による頭蓋内出血・脳挫傷・中枢神経系感染症などの続発性症状として生じることもあります。頭蓋内出血・脳挫傷・中枢神経系感染症などでは脳浮腫の影響で、脳内の容積変化が確認されるケースもあるためです。以下は、頭蓋内圧亢進につながる可能性がある脳浮腫の種類と概要を示します。
| 血管原性浮腫 | 血管の損傷によって血液脳関門が破綻し、血漿成分が流入して生じる脳浮腫 |
|---|---|
| 細胞性浮腫 | カルシウムイオンやNaイオンの流入によって細胞内の電解質バランスが変化し、貯留した水分によって生じる脳浮腫 |
| 間質性浮腫 | 過剰に生成された髄液が間質に漏出し、貯留した水分によって生じる脳浮腫 |
頭蓋内出血や脳挫傷では血管原性浮腫・細胞性浮腫の両方が発生して急激な頭蓋内圧の上昇につながるリスクもあり、意識的な対応が必要です。髄膜炎などの中枢神経系の感染症では間質性浮腫により、頭蓋内圧亢進を起こすリスクがあります。
頭蓋内圧亢進の検査・診断

頭蓋内圧亢進の診断では通常、医師による神経学的診察、画像検査、脳脊髄液検査などを実施して、原因の特定と程度の把握を目指します。各検査の概要と診断方法は、以下の通りです。
医師の評価
頭蓋内圧亢進が疑われる場合に医師は主に、以下の項目を診察します。
- 意識レベル評価
- 瞳孔検査
- 眼底検査
- 運動機能検査
意識レベルは、JCSやGCSで評価することが一般的です。瞳孔検査では、対光反射、瞳孔の大きさと形状、左右差の有無などを確認します。
眼底は、神経組織を肉眼によって診察できる部位です。眼底検査では携帯型の眼底鏡を使用して、視神経乳頭・網膜・動静脈の異常を確認します。
(出典:一般社団法人日本神経学会「神経学的検査チャート作成の手引き」)
ジャパンコーマスケールとは? JCSの特徴やGCSとの違いを解説
画像検査
頭蓋内圧亢進につながる病変を特定する目的で、CT検査とMRI検査を実施します。CT検査とは、放射線を使用して頭部の断面画像を撮影する検査です。CT検査はMRI検査と比較して短時間で実施できることから、緊急時の初期診断手段としても活用されます。
MRI検査は、強力な磁力と電磁波を使用して断層画像を撮影し、内部構造を確認する検査です。MRI検査では複数の撮像法を組み合わせて頭蓋内の構造や髄液の動態を観察し、病変の特定を目指します。
脳脊髄液検査
脳脊髄液検査とは、腰椎穿刺によって髄液圧の直接測定と髄液の採取を行う検査です。採取した髄液に対しては、以下の分析・検査を必要に応じて実施します。
- 外観観察
- 生化学検査
- 培養検査
- 髄液圧測定
外観観察では、色調や混濁の有無を確認します。髄膜炎の場合には髄液が、白みがかった色や黄色に変化するためです。出血がある場合に髄液は、赤色や黄色調に変化します。生化学検査ではたんぱく質濃度・細胞数・糖濃度などを測定し、感染症や炎症性変化の有無を確認することが通常です。
まとめ
頭蓋内圧亢進とは、頭蓋骨内の圧力が異常に高まる状態を指し、頭痛、嘔吐、うっ血乳頭の三徴候を特徴とします。急性期・慢性期いずれにおいても適切な対応が求められ、放置すると脳ヘルニアに移行するリスクがあります。診断には、神経学的診察、CTやMRIといった画像検査、脳脊髄液検査が行われ、原因の特定と早期治療が重要です。
転職やキャリアアップをお考えの看護師の方は、「マイナビ看護師」のサービスをご活用ください。看護業界に精通したキャリアアドバイザーがニーズに合った求人情報をご提案し、充実したキャリア形成をサポートしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
-

今話題のトラベルナース!短期間かつ高給与の求人が揃ってます!
-

転職先で給与アップしたい方へ★
年収500万円以上の高収入求人や応募のポイントをご紹介! -

人気の転職時期である4月に転職するメリットはたくさん!
-

働きながら綺麗になれる♪常に人気の美容クリニック求人をピックアップ!
-

企業でも看護師資格を活かして働けます!ワークライフバランス◎
-

シフト勤務の環境を変えたい方向けに、土日祝休みの求人をご紹介!
-

看護師さんの約半分は夜勤なしで勤務中!無理なく働ける夜勤なし(日勤のみ)求人をご紹介!