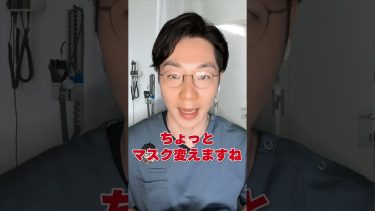生理食塩水は細胞外液と等しい浸透圧を持つ塩化ナトリウム水溶液で、主に医療現場で薬剤の希釈や輸液、洗浄に利用されます。また、生理食塩水はリンゲル液などを含む等張電解質輸液の一種で、輸液として5%ブドウ糖液などとは使い分けられます。
この記事では、生理食塩水の効果や副作用、作り方、ほかの輸液との違いについて解説します。看護師として生理食塩水の特性や適切な使い分け方が知りたい方は、ぜひこの記事を参考にしてください。
生理食塩水とは
生理食塩水とは、体液と浸透圧が等しい塩化ナトリウム水溶液を指す用語です。生理食塩水は、浸透圧が細胞の外にある体液(以下、細胞外液)と等しいことから、血漿などの細胞外液と同様に体内に残り、体液の補充に役立ちます。ここでは、生理食塩水の概要をさらに詳しく解説します。
生理食塩水の用途
生理食塩水は、人体との親和性が高い点が特徴で、さまざまな用途に用いられている溶液です。生理食塩水の用途は次の通りです。
| 注射液の溶解希釈剤 |
|---|
| 注射液などの溶解や希釈に生理食塩水を使用します。注射・点滴の薬剤による血管の炎症リスクを抑える効果があります。 |
| 輸液 |
|---|
| 細胞外液欠乏などが起きた際、生理食塩水そのものを体内に注入し、輸液として使用します。輸液は、皮下・静脈内注射もしくは点滴によって注入します。 |
| 創傷面や粘膜、皮膚、医療用器具などの洗浄 |
|---|
| 生理食塩水は鼻洗浄やカテーテルの洗浄などにも使われます。創傷面・粘膜・皮膚に対しては、湿布に用いる場合もあります。 |
生理食塩水の副作用や注意点
生理食塩水は人体と親和性が高く、リスクがない印象を持つ方もいます。しかし、生理食塩水を大量あるいは急速に投与すると、次の副作用が現れる恐れがあります。
- 血清電解質異常
- うっ血性心不全
- 浮腫
- アシドーシス
生理食塩水を投与する場合、異常を引き起こさないように、必要以上に投与速度を上げないのが基本です。また、残液は使わないようにしましょう。
ただし、熱中症や脱水症状など、状況によっては大量の生理食塩水を全開投与するケースもあります。大量・全開投与の際は、患者さんに異常を感じたら、症状の変化の観察とバイタルサイン測定を徹底しましょう。
特に、アシドーシスの初期は多くの場合無症状で、異常を見逃す恐れがあります。重度になると低血圧やショック症状を引き起こす可能性があるため、悪心や嘔吐、異常呼吸といった特定の兆候を見逃さないようにしましょう。
生理食塩水の作り方
生理食塩水は、塩分濃度0.9%の食塩水です。十分な設備や薬剤が準備できない状況であっても、1リットルの水に9gの塩を溶かすと低価格で簡単に作れます。
精製水が手に入らない場合は、煮沸した水もしくはペットボトルの水を使うとよいでしょう。煮沸した水を温度が高いうちに使うと、塩の溶け残りを防げます。
ペットボトルの水を使う場合、開栓前であれば水の容量を量る必要がなく、より正確な濃度で作れる点が便利です。たとえば、500ミリリットルのペットボトルであれば、おおよそ小さじ1杯(4.5g)の塩があれば作れます。
いずれの方法で作る場合も、使用時に患部との温度差があると痛みを感じる場合がある点には注意が必要です。なるべく痛みを感じないように使いたい場合は、温度を人肌程度(35~38度前後)に調節してから使用するとよいでしょう。
生理食塩水を含む等張電解質輸液とは

等張電解質輸液とは、浸透圧が体液とほぼ同じ電解質の水溶液です。生理食塩水に含まれているナトリウムと塩素も電解質のため、生理食塩水も等張電解質輸液の1種です。
別名「細胞外液補充液」とも呼ばれており、等張電解質輸液全般は生理食塩水のように細胞外液の補充に使います。ここでは、ほかの等張電解質輸液について解説します。
リンゲル液
リンゲル液は、塩化ナトリウムに加えて、塩化カリウムと塩化カルシウムを含む等張電解質輸液です。リンゲル液には、カリウム・カルシウムといった生理食塩水に含まれていない電解質が含まれています。ただし、血漿に含まれているHCO3-イオン(以下、重炭酸イオン)が含まれておらず、代わりに塩素イオンの含有率が高まっています。
生理食塩水の主な成分は塩化ナトリウムであり、塩素とナトリウムの含有量は同等です。一方、リンゲル液には、カリウム・カルシウムと結合した塩素イオンも含まれており、ナトリウムより塩素の含有量が多い点に特徴があります。
乳酸リンゲル液・酢酸リンゲル液
リンゲル液にアルカリ化剤を添加し、塩素イオンの総量を抑えた等張電解質輸液もあります。乳酸イオンを添加した溶液が乳酸リンゲル液、酢酸イオンを添加した溶液が酢酸リンゲル液です。
乳酸リンゲル液・酢酸リンゲル液は多くの種類のイオンを含み、リンゲル液より細胞外液に近い電解質組成を持ちます。乳酸イオンや酢酸イオンを添加することで、最終的には血漿に含まれる重炭酸が発生し、アシドーシスの補正に一定の効果が見込まれます。
重炭酸リンゲル液
リンゲル液に、乳酸や酢酸の代わりとして重炭酸イオンを添加したものが重炭酸リンゲル液です。重炭酸リンゲル液には、ビカーボンとビカネイトの2種類があります。
重炭酸リンゲル液には、ほかのリンゲル液には含まれていない重炭酸が最初から含まれており、乳酸リンゲル液や酢酸リンゲル液より、電解質組成がさらに細胞外液に近い点が特徴です。また、重炭酸リンゲル液には最初から重炭酸が溶液内に存在することから、リンゲル液のなかでもアシドーシスの補正がもっともスムーズです。
生理食塩水と5%ブドウ糖液の違い

5%ブドウ糖液も、生理食塩水と同じく細胞外液と等しい浸透圧を持ち、輸液に使われることがあります。5%ブドウ糖液と生理食塩水の違いは、細胞内に水を届けられるかどうかです。
5%ブドウ糖液は、細胞の内外に水分を補充できる溶液です。ブドウ糖液の水分は細胞外に残ったまま、ブドウ糖は細胞表面のグルコース輸送体(GLUT)によって速やかに細胞内に吸収されます。細胞内では、ブドウ糖は糖代謝によって水と二酸化炭素に分解され、細胞内にも代謝によって水が生成されます。
一方、生理食塩水では細胞内外に浸透圧差が発生せず、細胞外のみに水がとどまるため、細胞内への水分補充には利用できません。
輸液に使われる1号液~4号液とは?

輸液には、生理食塩水と5%ブドウ糖液を混ぜ合わせ、両者の特徴を活かしたものもあります。生理食塩水と5%ブドウ糖の混合液は維持輸液とも言われます。維持輸液に含まれるブドウ糖は代謝で分解され、浸透圧自体は細胞外液より低くなる点が特徴です。そのため、細胞内にも浸透しやすく、維持輸液の投与によって体液全体が増加します。
維持輸液は、ナトリウムの割合が高い順に、1号液~4号液の4種類に分かれます。1号液~4号液の特徴は次の通りです。
| 1号液(開始液) | カリウムを含まない輸液です。通常、病態不明の段階や小児の脱水症状の初期段階で使われます。 |
|---|---|
| 2号液(脱水補給液) | 主な用途は電解質の補給です。2号液には、細胞内に多く含まれる電解質が含まれています。 |
| 3号液(維持液) | 1日に必要な水と電解質の補給が主な用途です。不感蒸泄や排泄などで失われる水分を体全体に補給します。 |
| 4号液(術後回復液) | 浸透圧が低く、主に細胞内の水分補給に使われます。 |
医療現場でよく使われるのは、主に1号液と3号液の2種類です。細胞外液の補充を重視する場合には生理食塩水の割合が高い維持輸液が使われ、細胞内液の補充に重点を置く場合はブドウ糖液の割合が高い維持輸液が使われます。
まとめ
生理食塩水は医療現場で水分補給や創傷洗浄に幅広く利用されています。また、生理食塩水と同様に等張電解質輸液であるリンゲル液のなかでも、乳酸リンゲル液・酢酸リンゲル液や重炭酸リンゲル液はアシドーシスを抑えつつ細胞外液を補充するために使われます。また、生理食塩水と5%ブドウ糖の混合液は維持輸液と呼ばれており、割合によって用途が異なるのが特徴です。
マイナビ看護師は、看護師としてのキャリアアップを目指して転職を検討している方に向けて、無料で転職をサポートするサービスです。看護業界に精通したキャリアアドバイザーがそれぞれの希望やキャリアに合った職場を紹介しております。就職・転職を検討している看護師の皆さんは、ぜひマイナビ看護師にご登録ください。
※当記事は2024年9月時点の情報をもとに作成しています
-

今話題のトラベルナース!短期間かつ高給与の求人が揃ってます!
-

転職先で給与アップしたい方へ★
年収500万円以上の高収入求人や応募のポイントをご紹介! -

人気の転職時期である4月に転職するメリットはたくさん!
-

働きながら綺麗になれる♪常に人気の美容クリニック求人をピックアップ!
-

企業でも看護師資格を活かして働けます!ワークライフバランス◎
-

シフト勤務の環境を変えたい方向けに、土日祝休みの求人をご紹介!
-

看護師さんの約半分は夜勤なしで勤務中!無理なく働ける夜勤なし(日勤のみ)求人をご紹介!