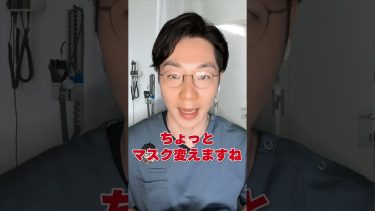腎不全は、生活習慣や遺伝などの要因により腎臓の機能が失われ、その結果さまざまな合併症にもつながる疾患です。慢性化すると人工透析や腎移植しか手だてがなくなり、最終的には死に至ることもあります。
この記事では、腎不全の概要を慢性・急性に分けて詳しく解説し、原因や重症度に合わせた看護・診療方針のポイントを紹介します。一度失われた腎機能は再生できない可能性が高いため、患者さんやご家族には発症予防や重症化予防の重要性を丁寧に説明しましょう。
腎不全とは
腎不全とは、腎臓の機能が落ち、余分な水分や老廃物を十分に排出できなくなった状態を指します。その結果、体内に不要な物質がたまり、心不全や代謝異常などさまざまな疾患にもつながります。
腎臓の主な働きは、「血液中の水分量」と「生命維持に必要な成分の濃度」の調節です。水分量や成分濃度の調節は、腎臓内の糸球体と呼ばれる毛細血管で行われています。この糸球体が炎症を起こし、血液のろ過がうまく進まないことなどが腎不全の原因です。
(出典:国立循環器病研究センター「腎不全」)
腎不全は一般的に「慢性」と「急性」とに分類され、腎臓の機能低下が徐々に進んだ状態を「慢性腎臓病」、急激に進行した状態を「急性腎障害」と呼びます。ここからは、「慢性」と「急性」の概要や診療方針の違いについて解説します。
慢性腎臓病(CKD)とは

慢性腎臓病(CKD)とは、腎臓の働きが通常より60%以下に低下し、尿たんぱくが慢性的に続く病態を指します。ステージが末期に至ると、透析導入や腎臓移植など腎代替療法が必要になり、患者さんの身体に大きな負担を与えます。尿異常などの兆候を見逃さず、早期発見につなげることが重要です。
(出典:厚生労働省「慢性腎臓病」)
慢性腎臓病の診断は、以下のいずれかまたは両方が3か月以上持続する場合に行われます。
- 尿異常(特に尿たんぱく)など腎障害の存在が明らか
- 糸球体の機能を示すGFRが60以下
(出典:厚生労働省「4 慢性腎臓病(CKD))
GFRは、血液検査で測定できる血清クレアチニン値と、年齢・性別から計算できます。GFRはどれくらいの老廃物を尿に排出できるかを示す値であり、この値が低いほど腎臓の機能が低下していると分かります。
慢性腎臓病の重症度分類
慢性腎臓病の重症度は、5段階のステージに分けられ(G1〜G5)、ステージに合わせた診療方針が示されます。
重症度は、原疾患区分、腎機能を示すGFR区分、尿たんぱく区分の3つの区分を合わせて評価され、死亡・末期腎不全・心血管死亡のリスクがステージごとに示されます。
(出典:厚生労働省「4 慢性腎臓病(CKD))
慢性腎臓病の看護・診療方針
慢性腎臓病の看護・診療方針には、3つの目的があります。
(1)末期腎不全に至ることを防ぐ、または進行を遅らせる
(2)心筋梗塞や脳卒中など心血管疾患の発症・重症化を防ぐ
(3)代謝異常などの合併症を防ぐ
上記3つの目的を達成するため、看護・診療方針は「発症予防」と「重症化予防」の観点から患者さんの病状に合わせて示されます。
・発症予防
糖尿病・高血圧など慢性腎臓病の発症リスクが高い患者さんに対しては、早期から生活習慣改善や食事管理の指導を行います。CKDを早期に発見し適切な治療を行えば、透析が必要な患者さんを減らすことにつながります。
・重症化予防
CKDが進行し腎機能が低下すると、老廃物が体内に蓄積し、尿毒症や高カリウム血症などの代謝異常が生じます。また、余分な水分が排出されないことにより心臓への負担が大きくなり、心血管系疾患のリスクも高まります。すでにCKDを発症している患者さんに対しては、食事療法や薬物療法による対処で、心血管系疾患・代謝異常の発症や重症化を予防することが大切です。
(出典:厚生労働省「4 慢性腎臓病(CKD))
急性腎障害(AKI)とは

急性腎障害(AKI)とは、数時間~数日という短期間で急激に腎機能が低下し、「尿から老廃物を排出できない」「体内の水分が過剰になる」といった状態を指します。
急性腎障害の診断は、以下のいずれかに該当する場合に行われます。
・血清クレアチニン値が0.3mg/dl以上上昇した(48時間以内)
・血清クレアチニン値が基礎値より1.5倍以上の増加した(7日以内)
・尿量が6時間にわたって0.5ml/kg/時間に減少した
(出典:国立循環器病研究センター「AKIの定義)
血清クレアチニンは体がタンパク質を分解するときにできる老廃物で、通常は尿と一緒に排出されます。腎機能が低下することで血清クレアチニン値の濃度上昇が見られるため、腎機能評価の指標として使用されます。
急性腎障害の病期分類
急性腎障害は、血清クレアチニン値と尿量から3つのステージに分類されます。加えて、障害がどの部分に起きているかにより、「腎前性」「腎性」「腎後性」の3つに分類されます。
・腎前性
腎臓そのものに障害はなく、腎臓への血流が低下したことにより腎障害に至ります。主な原因は脱水や血圧低下などです。
・腎性
腎臓そのものに障害があります。障害が起きている部分により「血管性」「糸球体性」「尿細管・間質性」の3つに細分化されます。
・腎後性
腎臓から出た尿路の狭窄・閉塞により腎障害に至ります。両側水腎症などが原因です。
(出典:国立循環器病研究センター「AKIの病気分類」)
急性腎障害の看護・診療方針
急性腎障害では、腎機能低下の原因を取り除くことで回復する可能性があるため、病因に応じた看護・診療方針が示されます。
| 腎前性 | 腎血流の低下が原因のため、捕液(輸液・輸血など)による治療が行われます。 |
|---|---|
| 腎性 | 障害が起きている部位を特定し、原疾患の治療(免疫抑制や抗体除去など)を行います。 |
| 腎後性 | 尿道の狭窄・閉塞を解除するための治療が行われます。 |
詳しい診療については、日本腎臓学会の「AKI(急性腎障害)診療ガイドライン2015」を参考にしてください。
慢性腎臓病療養指導看護師とは
慢性腎臓病療養指導看護師(CKDLN)とは、熟練した看護技術と慢性腎不全知識を用いて水準の高い看護ケアを行う看護師を指します。平成15年度より導入された認定資格であり、慢性腎臓病における看護ケアの質の向上を目的としています。
慢性腎臓病療養指導看護師の役割
①慢性腎臓病療養生活支援において個別的ケアの実践と評価ができる。
②慢性腎臓病療養生活支援に関する知識と技術を持ち、安全で安楽な療養環境を提供できる。
③患者・家族の長期療養生活を効果的に支援できる。
④実践的モデルを示すことによって医療チームのリーダーシップを発揮する。
⑤慢性腎臓病看護の質向上に主体的に取り組める。
(引用:一般社団法人日本腎不全看護学会「慢性腎臓病療養指導看護師(CKDLN) CKDLNとは」)
CKDLNの受験資格
下記の6項目を満たす者
1.日本国の看護師の免許を有すること(准看護師は不可)
2.一般社団法人 日本腎不全看護学会正会員歴が通算して3年以上あること
3.慢性腎臓病看護領域実務経験が年度末(8月31日)の時点で通算3年以上あること
4.看護実務経験が8月31日現在で通算5年以上あること(慢性腎臓病看護領域実務経験3年以上を含む)(実務経験年数は、申請時ではなく、8月31日(年度末)での見込みも可。)
5.慢性腎臓病看護領域(CKD・血液透析・腹膜透析・腎移植)の看護実践の事例報告を1例提出のこと(管理的業務に従事している場合は看護管理事例を1事例提出するのも可とする)
6.受験資格ポイントが20ポイント以上取得できていること
ポイント取得対象の学術集会・セミナーなどの参加証または領収書(ともに氏名が確認できるもの)を受験申請時まで保管し、証拠書類として提出する。
(引用:一般社団法人日本腎不全看護学会「慢性腎臓病療養指導看護師(CKDLN) 受験資格・申請手続き」)
まとめ
腎不全は、患者さん自身の自覚症状なく進行していることが多く、いったん慢性腎不全になると、失われた腎機能を回復することはできません。日常生活にも支障をきたすため、早期発見が大変重要であり、ステージや原因に合わせた適切な治療を行うことが求められます。
「マイナビ看護師」は、看護師の皆さんが自分らしく輝くための転職サイトです。看護業界に精通したキャリアアドバイザーが、書類添削から面接対策まで無料でサポートしています。看護師さん一人ひとりの希望に合った働き方を叶えるため、マイナビ看護師をぜひご活用ください。
※当記事は2022年9月時点の情報をもとに作成しています
-

今話題のトラベルナース!短期間かつ高給与の求人が揃ってます!
-

転職先で給与アップしたい方へ★
年収500万円以上の高収入求人や応募のポイントをご紹介! -

人気の転職時期である4月に転職するメリットはたくさん!
-

働きながら綺麗になれる♪常に人気の美容クリニック求人をピックアップ!
-

企業でも看護師資格を活かして働けます!ワークライフバランス◎
-

シフト勤務の環境を変えたい方向けに、土日祝休みの求人をご紹介!
-

看護師さんの約半分は夜勤なしで勤務中!無理なく働ける夜勤なし(日勤のみ)求人をご紹介!